きのうは「たたみ」の発展過程の探究を考えましたが、
写真は同じ、おきなわ郷土村に建てられている復元古民家・与那国の家。
で、本日はほとんど製材していない柱と梁を縄、もしくは
つる性植物で結束させている「架構」を見たいと。
先日も、三内丸山の縄文復元建築と吉野ヶ里の弥生復元建築の
「木組み構法」の違いを見たのですが、
あれは年代的にはそれぞれ、5,000年前とか1,800年前とかの想定。
それに対してこちらの建物は、基本的には移築復元とされているので、
ごく近年まで実際に建っていた住宅ということ。
どんなに古く考えても、100-200年程度の過去ということになる。
であるのに、木組みの構法として結束がつる性植物。
しかも構造の建材・木も未製材の自然木が使われていました。
壁や床、屋根の骨格についても、竹を組み上げて造作していた。
製材した材料ではないので、直線的な均整感よりも、
それこそ竪穴住居的なバイタルな印象に近い建てられよう。
自然派志向的には究極的なエコロジーを感じる(笑)。
しかし、きっと建てた人たちには止むにやまれぬ選択だったのでしょう。
こういった「民家」は、構造部分だけは大工職人が基本を作って
そのあとは建て主・住まい手が材料集めも含めて
DIYとして「施工」まで行ったのが普遍的なありようだったのでしょう。
もちろん近代国家が「建築基準法」的に制約を加えたものでもなかった。
しかしその「依頼」には当然「手間賃」費用負担は当然あっただろう。
また、与那国島にそういった大工職人が定住していたとも考えにくい。
そこに住むことを人生選択した人間が自分自身のため、家族のため、
手作りで挑戦していたに違いない。
そういうことで考えれば、主体構造である柱と梁を結合させるのに
複雑な工具・建築知識を必要としない建て方として、
こういった「構造」は、自然発生的でわかりやすかったでしょうね。
たぶん材料の類は、その建物周辺から自分ですべて探し出してきたのでは。
アイヌのチセの場合も、家を新築するのは結婚の時点が多く、
材料は新郎が自分で集めてくるというのが「しきたり」だったとされる。
定かではないのですが、想像としてはそのように考えられる。
その時点で建てられていた家の構造を見て、
それを「モデル」として「見よう見まね」で建てたというのが自然。
施工についても、近縁者が労働奉仕していっしょに作ってくれた(笑)。
きっと新婦はそういう助けに来てくれた人に手作りの食事を作って
感謝の気持ちを表した、っていうような風景が思い浮かびます。
現代のように、ひたすらお金に換算した建築のありようと、
どっちが家づくりで「楽しいか」は、なんとも言えないでしょうね(笑)。
Posted on 8月 24th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究

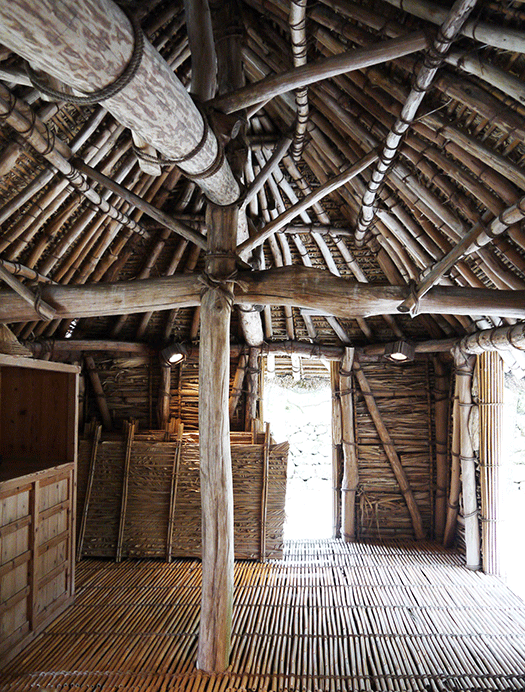






コメントを投稿
「※誹謗中傷や、悪意のある書き込み、営利目的などのコメントを防ぐために、投稿された全てのコメントは一時的に保留されますのでご了承ください。」
You must be logged in to post a comment.