きのうの続きです。
播州・福崎町の古民家・三木家住宅の「ハレ」の空間。
姫路藩の「大庄屋」として、藩主とか代官とかを接遇する「間」がある。
日本住文化ネイティブのような「南面座敷」であり、庭が造作され
その眺めを、床の間・床柱を背にして茶を喫しながら愛でる。
そういうような武家的精神生活表現として、典型が形成された。
北海道住宅ではこういう「和のデザイン」要素は
ごく初期には「日本伝統文化移植」として一部でつくられたけれど、
そういう文化性以上に本来的な「住性能」に興味が圧倒的集中した。
そもそも「格式重視」という「伝統規範」圧力が社会的に形成されなかった。
新開地である積雪寒冷地域では、住人がほぼ全員「移住者」であり、
伝統もなにも、「仏壇を背負って」移住したようなケースは稀だった。
そういった「家」意識は本州社会に残置させて新天地が北海道では展開した。
伝統規範形成より前に、ここで安定的に生存できるかどうか、
根源的生存環境の克服のほうが緊急的だったのだ。
とくに「縁側」という空間はその過程でほぼ棄却されてしまった。
それに伴って日本的な「庭」空間意識もまったく変容せざるを得なかった。
ごく初期に南面する庭と縁側という「伝統スタイル」を作った住宅では、
半年、積雪に閉ざされた庭を「柱が積雪荷重で折れるのではないか?」と
不安にハラハラしながら「眺める」ということになった。
縁側はヘタをすれば冬にはスケートリンク状態にもなった。
・・・というやむを得ない事情から縁側という日本住文化の
清華のような空間が、北海道ではまったくキャンセルされてしまった。
外部と親和する半外部という存在は忘却の彼方へ飛んでいった。
そういう寒冷地では、住意識では居間中心の大空間化が進展した。
熱環境的な必要性から、空間はなるべく一体的な環境が志向された。
そうすると小間割り思想からの座敷需要も激減し「床の間」も消滅する趨勢。
・・・で、そういう「住宅革命」を経過した新常識を持った北海道人は、
めずらしきものとして写真のような空間を「愛でる」ことになる。
写真のような「暮らし精神」を異郷風景として見るようになっている。
一方で明治以降の「都市化」「文明開化」的な「洋風志向」も
公団住宅LDK文化として日本本州社会全般でも同時進行していったのでしょう。
結果として居間中心型の住文化に移行したのが日本の主流だろうけれど、
その由縁にはこの2つの方向性があったのだと思う。
やはりこうした空間には、蒸暑の夏への対処法が示されていて、
縁側では、緑や周辺環境に対して「開放的」なライフスタイルが明示され、
蒸暑気候を耐えるため庇の長い軒の出での日射遮蔽が工夫された。
一方の床の間空間では「心を静める」みたいな精神性が追究されたように思う。
心頭を滅却すれば火もまた涼し、というような禅的心境で
ここちよい「薫風」が床の間付きの室内に涼を呼ぶ、みたいな。
で、日本人的精神性という部分、北海道人はこの「空間対応」でズレがある。
いわば日本文化として蒸暑気候対応の積層した住文化に対して
受容すべきかどうか、ふと迷ってしまう自分がいるのですね。
「いいけど、北海道じゃムリだよなぁ・・・」という内語はやむを得ない。
そこから北海道での「高級住宅」のしつらいについて、悩むことになる。
しかしこういう寒冷と蒸暑の対話から、次代の「空間性」が始まることもトレンド。
考えてみるとオモシロい住宅の歴史時間にわれわれはいるのかも知れない。
Posted on 7月 13th, 2020 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 住宅性能・設備, 日本社会・文化研究

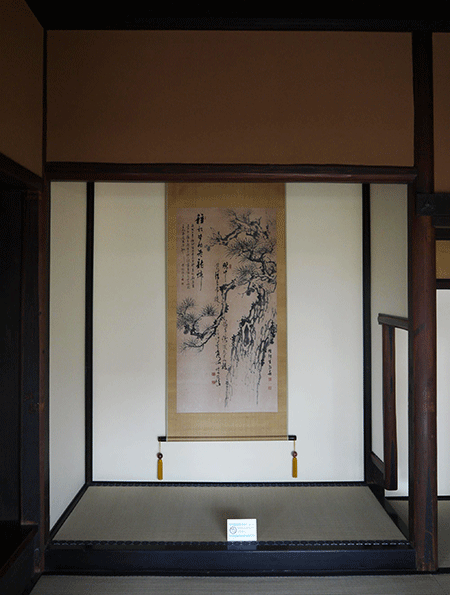








コメントを投稿
「※誹謗中傷や、悪意のある書き込み、営利目的などのコメントを防ぐために、投稿された全てのコメントは一時的に保留されますのでご了承ください。」
You must be logged in to post a comment.