本日は歴史関係の書評がらみネタです、あしからず。
最近「日本国紀」という通史をやや右派系作家・百田尚樹さんが書いて
話題になっている。幻冬舎という商機に敏感な出版社ということで
どんなふうになるかと注目しています。
そこそこ売れているようで、仙台空港の書店員さんに聞いたら即座に
「ああ、けっこう売れていますよ」と話してくれて
書棚に案内してくれたら、なんと10冊くらいが平積みされていた。
30万部初版印刷というのはあながち誇張ではないかも知れない。
紙の単行本がこれくらいの規模で出版されるということは最近珍しい。
学問としての日本史は、文献史学偏重の悪影響で専門時代領域分化が極端。
いわゆる「通史」というような領域は軽視されてきている。
違う著者の「思想」を断片的につなぎ合わせる理解しか、
いまのニッポン人には情報が提供されていない現状がある。
もちろん特定の思想によってのみ歴史が理解されるべきではないのは自明。
多様な理解、人々の動きというモノを把握する必要がある。
現代社会が単一的な思想要因だけで成立しているわけではないように。
しかし、戦前と戦後では日本史理解に巨大な溝があるのも事実。
戦争の結果、それまでの知見とその領導した学者さんたちが一掃され、
どちらかといえばマルクス主義に基づいた歴史認識をもった人たちが
タナボタのように、また無批判的に主流の位置を占めたのも厳然たる事実。
それはそれでやはり極端に振れすぎているという反省が始まってきている。
この本に対してはさっそく「コピペだらけだ」「Wikipedia頼り」などの批判がある。
そういう批判は大いにあって良いけれど、一作家がこういう取り組みをしたという
そしてそれが一定の社会的評価を得ていることは認識する必要がある。
まぁまだ途中ではありますが、学問的と言うよりも
流れ作業的な部分も感じられて、通史モノ表現の難しさも垣間見えてはいる。
ただ、断片的に書かれている作者による「意見」の類は面白く読むことができる。
で、この本とは別に最近、読み続けているのが写真の1冊。
「日本」という国号が定まった時期以前の活発な列島ー朝鮮半島地域の
社会政治状況というのに、最近大きな関心が湧いてきて仕方ないのです。
朝鮮半島諸国での相克、権力争いのなかで「倭国」は重大な関心を持ち
積極的にその相克に関わっている。以前にも書いたとおり「鉄資源」の交易というのが
その大きな動機・要因であったことが推定されるのです。
それは農耕の必須道具にも関わり、同時に戦争の道具でもあるので、
容易に戦乱を呼ぶ契機になっていた様子がわかる。
それにしても朝鮮半島と列島西部地域というのは、どうも社会的一体性を感じる。
ヤマト朝廷は神武東征の故事に見られるように
九州を出自として畿内地域に権力を広げたというのが正史でしょうが、
もうひとつの選択肢として、海峡を越えて朝鮮半島にも覇を唱えるというのも
いわばごく自然な志向性としてあったことが推測できる。
きっとこの時代には半島と列島ではコトバもふつうに通じていたのではないか。
米作農耕はこの列島社会では最初から朝鮮半島からの「移住者」社会組織が
その基本単位であって、そのマザー社会へのこだわりが強かったと思われる。
もし神武が東征ではなく西征、もしくは北征を行ったら、というイフも想像できる。
そういう歴史事態があれば、半島と列島は一体の「クニ」になった可能性もある。
この時代の活発な「交流」には想像力が強く刺激されます。
Posted on 11月 28th, 2018 by 三木 奎吾
Filed under: 歴史探訪

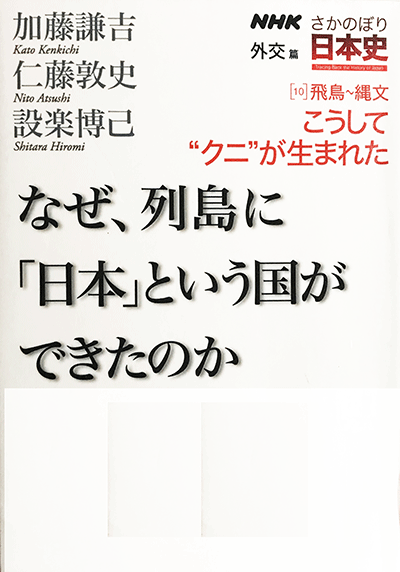






コメントを投稿
「※誹謗中傷や、悪意のある書き込み、営利目的などのコメントを防ぐために、投稿された全てのコメントは一時的に保留されますのでご了承ください。」
You must be logged in to post a comment.