日本社会では家は「永続」的な概念が強い。
「一所懸命」というコトバが示すとおり、家族がその私有の拡大を
長い年月を掛けて追究する社会を作ってきた。
親から子、孫へと資産を受け継がせることが正義。
家は家系の永続基盤の財であるという認識が強くあり、
歴史的に放火の罪業の重さは「放火殺人」と殺人と並列だった。
一所懸命への最大の暴虐だと考えられてきた。
一方、上の写真は東京国立博物館所蔵の「蝦夷島奇観」(1810年)から。
北海道の先住の人々の「住宅の風習」のひとつに
死者の家を焼くというものがあると、先日の古代住宅セミナー発表。
先住の人々には「火」に個人やその血統属性が認識されていて
夫婦であっても、その炉の火については不可侵性があったとされる。
炉や、擦文文化期までの「かまど」の火は、その「主人」だけが管理し
夫婦であっても別の火を使い続けていた可能性があるといわれる。
夫が先に亡くなったとき、妻が夫の火を世話することはできなかった。
火は血統の純粋性を表徴するものであって、同一血統だけが受け継げて
それ以外の血統はそれを受け継げなかったとされるのだ。
火を管理している人間が死んでその火を受け継ぐ人がいないとき、
その「火の葬儀」として、家そのものを焼却させたのだと。
下の写真は「擦文文化」期の竪穴住居跡ですが、
発見される竪穴の実に3割がこの写真のように建材が炭化している。
これは、死者の葬儀と「火の葬儀」も同時に行った痕跡。
住宅は、その死者と火に強く付属するものであって、
焼却して家もまた「葬儀」されたのだというのですね。
「火の血脈」は、婚姻関係からすらも個人を引き離し
より大きな「血統組織」に帰属させていた。資産というものが
「家族」の私有ではなく、血統組織社会共有のものと認識されていた。
それがいわゆる「部族社会」であり、「私有」概念が育たなかったのだ。
このことが耕地をはじめとした財の拡大発展を阻んできたとされる。
現代の住宅とはなんだろうか。
永続的な使用という意味合いは、核家族化の進展で薄れてきた。
生業も「受け継ぐ」という概念は希薄化する一方。
それに対して一方で「個人主義」という意識は強まっている。
家は個人の生き方、ライフスタイルの最大の「表現」。
住宅金融公庫システムという未曾有の「家を建てやすい制度」が機能し
人口減少が必ずしも住宅建設の減少とはならない可能性もある。
今進行しているのは、現代での生き方の大きな変化なのだと思う。
先住の人々の「火=いのち」「家=生き方」という考えもまた
なにか本質的なことの示唆に富んでいると思う。
Posted on 12月 31st, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究

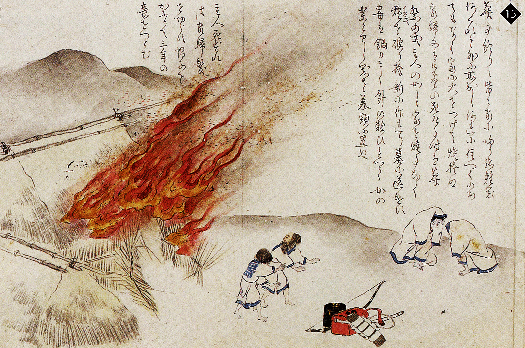







コメントを投稿
「※誹謗中傷や、悪意のある書き込み、営利目的などのコメントを防ぐために、投稿された全てのコメントは一時的に保留されますのでご了承ください。」
You must be logged in to post a comment.