「王羲之を超えた名筆」という書が日本で公開されている。
顔真卿さんという一般の日本人には馴染みのない名前ですが、
中国の人たちにとっては、その漢字文化の究極を表しているようです。
以下インターネット上で見られた「美術手帳WEB」の案内の要旨。
「中国において、東晋時代(317–420)と唐時代(618–907)は、
書法が最高潮に到達したとされる時代。そして「書聖」とも呼ばれる
王羲之(おうぎし)が活躍した東晋時代に続いて、唐時代には虞世南(ぐせいなん)、
欧陽詢(おうようじゅん)、褚遂良(ちょすいりょう)ら
初唐の三大家が楷書の典型を完成させた。
そして顔真卿(がんしんけい)は三大家の伝統を継承しながら、
「顔法」と称される特異な筆法を創出。王羲之や初唐の三大家とは異なる
美意識にもとづく顔真卿の書は、後世に大きな影響を与えた。」
というように紹介されていました。
たまたま東京出張の機会に、ちょっと見てみるか、
というような軽い興味で東京博物館に行ったけれど、
顔真卿の《祭姪文稿(さいてつぶんこう)》という名書を見るには
なんと、行列3時間ということだったので、
そこまでの強い思いがあるわけでは無論ないので、体感は諦めた。
しかしそこを起点にして、こういう中国史での「芸術」について
考えたりし始めています。
中国の山水画の類というのは、どうも日本人にはいま馴染みがない。
テーマが老荘の思想の極致を表現する、みたいな
なまの人間の叫びを感じさせるテーマではないために、
人類的共感としてはどうも感受しにくい。
個人的にわたしはそう思い込んでいるようです。
ただ、この「顔真卿の《祭姪文稿》」の紹介エピソードからは
この生きた個人、顔真卿さんという人物の個性とか息づかいというものが
立ち上ってくるように感じられました。
「乱によって従兄とその未子を亡くした顔真卿が亡骸を前に書いたという。
冒頭は平静に書かれているが、しだいに気分の高まりや激情が見られる筆致となり、
書き間違え、行そのものが曲がっている部分なども現れる、劇的な書」
というような紹介なのですが、実際にポスターなどでも
そういう書き間違えの部分などもあって、
激した感情というものが強く感じられてくる。
書というものに馴染みがなかったのですが、そういう劇的シーンが
感情移入されてくると、ようやく見方のスジがみえる。
まぁ入門としては貴重な機会だったかなと、見ることはなかったけれど
ふしぎに納得感が広がってきています(笑)。
しかしこの顔真卿の《祭姪文稿》は
国共内戦を経て、台湾に大量に貴重な文物が移転し、
「故宮博物館」が北京と台北にあり、そしてこの書は
なかなか公開されることがなくて、海外に出たのは
アメリカに次いで日本になったという経緯だと言うこと。
そういう経緯から中国本土のひとたちからは、
これが日本に行かなければ見られないことへの残念感が盛り上がったという。
しかし、旧正月休暇で実物に触れてきた人たちの口コミSNSなどで、
その素晴らしい「体験」への感動が多く語られているとのこと。
中国は繰り返し「易姓革命」が展開した。
それに対して日本は長く一体的国家意識が天皇制とともに継続した。
そういう社会の相違から、誤解も発生するけれど
こういう文化面での思わぬ局面も生まれるのだと興味深かった。
Posted on 2月 20th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究

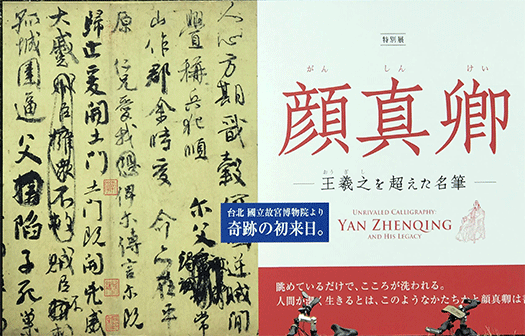






コメントを投稿
「※誹謗中傷や、悪意のある書き込み、営利目的などのコメントを防ぐために、投稿された全てのコメントは一時的に保留されますのでご了承ください。」
You must be logged in to post a comment.