さてシリーズっぽく紹介してきた札幌のビルダー・棟晶さんの
「新住協プロトタイプ2.5×6間」タイプ取材ですが、
拙ブログを見て「ぜひこの建物をみたい」という希望を寄せられた
宮城県大崎のビルダー・高橋建設・高橋社長がきのう来札されたので、
ご案内する名目でわたし自身も2.5×6間空間寸法の体験の
いい機会と考えて訪問してきました。お忙しいなか、
お付き合いいただいた棟晶・斉藤さんありがとうございました。
ということで、わたしがいちばん気になっていた空間に
みんなで座っての空間いごこちチェックであります(笑)。
<図面左の赤⬇部分スペース>
斉藤さんのお話では、当初は食堂と見立てていたスペースとのこと。
しかしやや寸法が足らない感じなので、鎌田紀彦先生から
家事室スペースに用途変更指定が来て、
壁にも奥行き60cmのテーブル板を嵌め込んだということでした。
でも実際に大の大人が3人で入り込んで見ましたが、
奥行き80cm超ほどのテーブルを挟んで対面していて、
そう大きく違和感は感じられなかった。
本格的に対面型の奥行きの狭めの定置座椅子を双方に配置して
テーブルを70-75cm程度に収めれば、
コンパクトな食卓、現代茶室、茶の間という用途利用に
ムリはないと感じられました。食堂店舗で見られるボックス席感覚。
むしろ、人と人の距離が親近感を増幅させるような印象を持った。
その場合、奥の壁に嵌め込んだ面板は60から45程度にカットしたい。
最近のドンキホーテなどの商業店舗でも狭さが
大きく意味を持ってきている現実を見ると、
住宅でも広さ拡大追究に見直しがあってもいいように思われた。
これも最近、わたし自身が住宅面積が2人で83坪から
2人で25坪弱にコンパクト化した体験からも有効と感じる次第。
この食に関わる住まいの「コアスペース」の感覚を受容すると、
残余の2.5×6間寸法の空間が、たいへん機能的と感じられました。
住まいのなかでの空間の密度にほどよいオンオフができて
狭さと広さにメリハリ、コントラストが効いてくると気付く。
狭めの空間にも人の心理にプラスに働く面があると。
考えてみればこれは戦国期に千利休さんが試してきたことでもある。
茶を喫し、食をたのしむ空間として日本の寸法感覚は進化した。
そういえばちゃぶ台円形テーブルなどの合理的空間感覚も
日本人は民族性として持っている。
上の写真は対面しているキッチン側から撮影しましたが、
手前側には配膳可能な平面も確保されているので、
食の空間としての機能性は十分に満たされているといえます。
で、そこが決まると、他のスペースは想像以上に広く感じる。
図面左側2階の⬇部分は子供室想定の個室2つですが、
こっちも両方向から使える収納家具造作を挟んでほどよいスペース感。
面積的には「約4.2畳大」ということですが、ベッド・机が入って
ちょうどいい感じに収まりそうですし、
反対側の夫婦寝室との間には階段を取り込んだ開放空間が広がる。
前回体感できなかった空間スパンが、少人数でしっかり確認できました。
聞いたら、さっそく売却が決定もしたそうですし、
いろいろな反響も出てきているとされていた。
新住協鎌田先生はいま4間4間プランに集中されているそうですが、
さぁ、ユーザーと市場はどう判断するのか、
興味が深まってきております。
Posted on 3月 13th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング
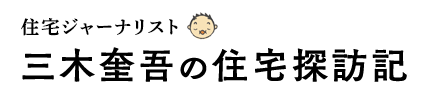
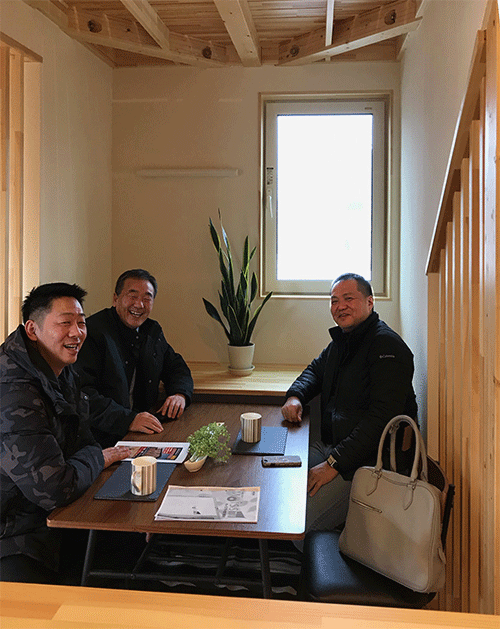

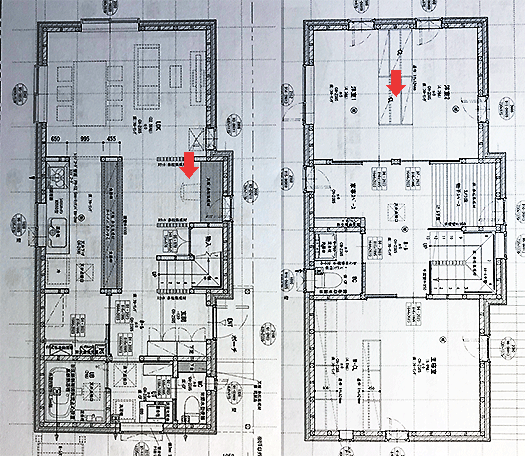




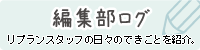
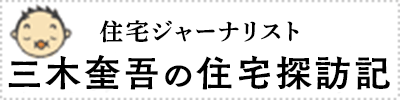
コメントを投稿
「※誹謗中傷や、悪意のある書き込み、営利目的などのコメントを防ぐために、投稿された全てのコメントは一時的に保留されますのでご了承ください。」
You must be logged in to post a comment.