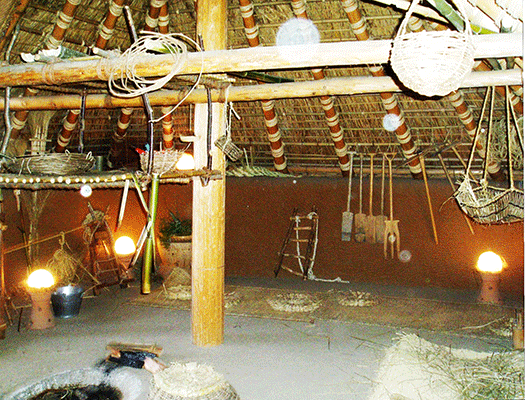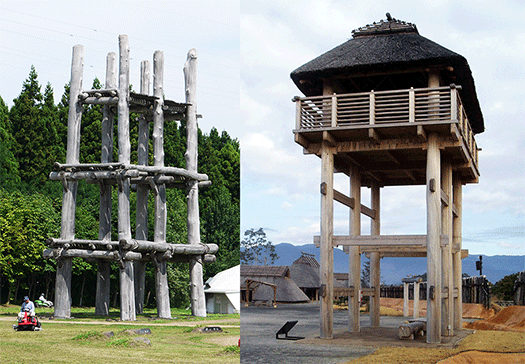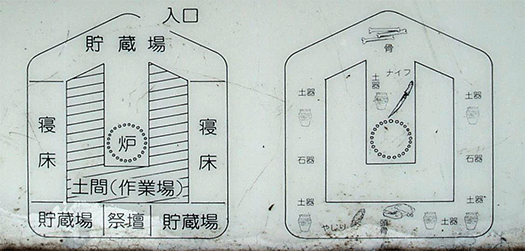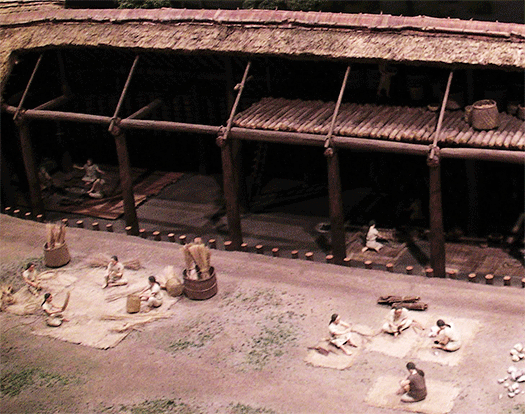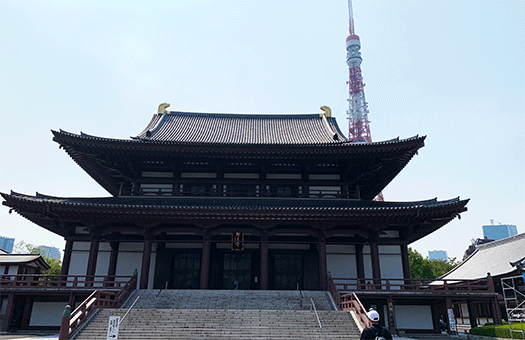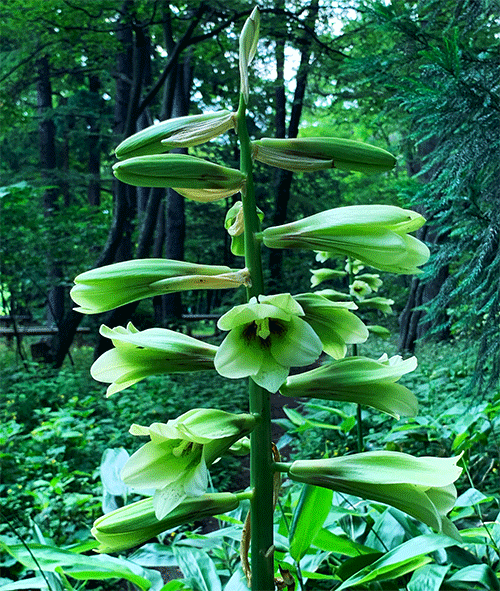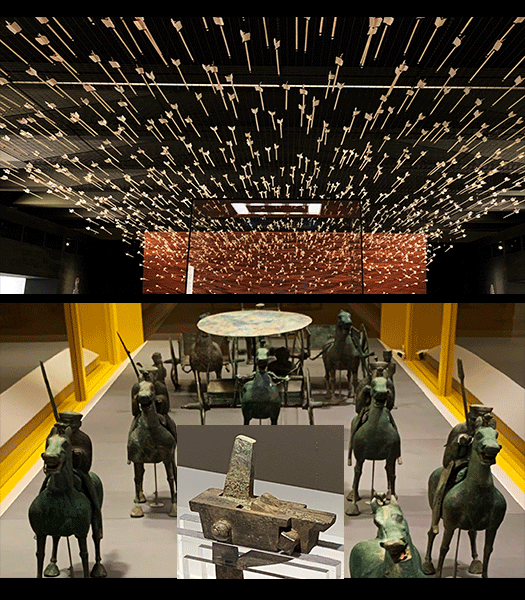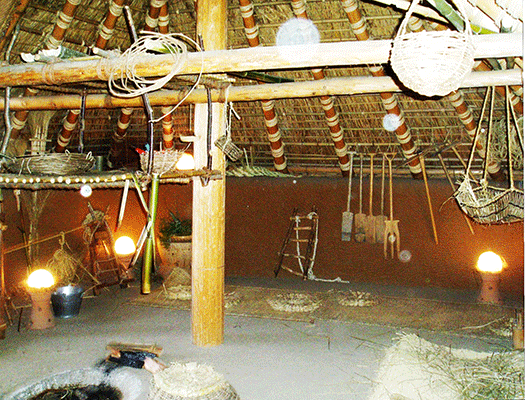
北海道の考古遺跡群はDNA的には縄文の残滓が色濃い。
縄文の人々は、アジアに進出した人類の中でも
いまから4万年前くらいに古層で枝分かれした人々という説がある。
この縄文の人々が日本人のベースを作って、
現代日本人には縄文人の特徴を示す遺伝子型が12%程度認められるとのこと。
それに対して大陸から渡来しただろう弥生文化様式の人々は、
日本列島への渡来としては、第3波を形成する人々という。
だいたい3千年前くらいから列島にきて、弥生的生産様式、
コメ生産に特化した社会を形成した人々だったのでしょう。
その掉尾を飾るのが、百済国家からの列島への集団渡来なのだと。
で、九州・吉野ヶ里では「環濠」で他と明瞭に区切られた
支配ー被支配という関係が明瞭な社会として出現している。
建築としては、高床式の「敷居の高い」建築が支配も表現していた。
ただし、日常生活の住居は支配層も竪穴住居だったとされる。
で、写真上のような畳状の敷物付きのベッドが復元されていた。
見学したのは、いまから15年程度前で、
最近、古建築探訪の記録写真を整理していて気が付いた。
この竪穴住居は「王の家」とされるものの内部で、
縄文の竪穴と違って地面に1段段差を付けたりしているので
「身分制」ということが建築としても表現されたものか。
ほかの竪穴でも下の写真のように、「むしろ」状の敷物が多く復元されていた。
やはりコメ生産技術に特化した社会として、ワラを利用した
生活備品というものが同時進化した様子をみることができる。
畳の素材はイ草ですが、初源の歴史ではどういう素材利用だったのか?
全国畳産業協会のHPで「畳の歴史」コーナーで以下の記述。
〜日本ならではの敷物「畳」が貴族階級から庶民へと普及するまで。
中国伝来のものが多いなかで、畳は日本固有の敷物。その歴史は
「菅畳八重」「皮畳八重」などの記述がある古事記にまでさかのぼります。
まだ畳床などはなく、コモなどの敷物を重ねたものと推測されます。
現在の畳に似た構造になったのは平安時代。板敷に座具や寝具として置く
使い方で、使う人の身分によって畳の厚さやへりの柄・色が異なりました。〜
ということで、古墳時代3世紀を想定しているこの吉野ヶ里展示で
使われている「畳の原初」というのは、暗示的ということで了解すべきか。
畳というのは、日本オリジナルの敷物ですが、
なぜこのようなインテリア装置が発展してきたのか、
コメ生産と周辺繊維質素材との相関だけでは他国との相違が説明できない。
やはり高温多湿という独特の気候風土が関係したのでしょうか?
敷物自体は人間の皮膚感覚としての必然としてそれぞれで進化した。
いろいろな可能性が考えられる中で,日本社会では畳が選択された。
その選択が進むと、独特の文化風土としても昇華発展もしたのでしょう。
なかなかに興味深いですね。
Posted on 8月 12th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »

人間性のごく基底的な感性領域に「帰巣本能」がある。
なぜかWikipediaにはこの項目がない。で、アンサイクロペディアによると
〜帰巣本能(きそうほんのう)とは、生まれた場所や過去に過ごした場所へと
戻ろうとする本能的行動。
人間の帰巣本能は雌雄で大きく異なり、基本的には男性の方が強い傾向にある。
また年代によっても左右され、十代半ば以降で強まるが六十代以降は
弱体化するとされている。ただしこれはあくまで帰巣衝動の弱体化であり、
機能自体はほぼ残るという説もある。〜
というように書かれている。
住宅ということを主要テーマにして生きてきた心理の奥底に
この「帰巣本能」ということが根深くあるのではないかと思っている。
人間は帰巣することで、さまざまな社会ストレスを癒して生き延びてきた。
住宅の最深の意味合いは、そこにしかないでしょう。
で、とくに住宅の外観について考えるとき、
いつもこの「帰巣本能」という無意識の「基準」を考えている気がする。
やっぱり住宅は「帰ってきたいなぁ」というメンタルへの訴求「性能」がほしい。
どんなにモダンデザインの住宅であっても
この基準自体は変わらないと思う。
この「帰りたくなる」ということのデザイン的な追求の仕方は
それこそ千差万別なのだろう。
人間の生きた数だけ「帰りたくなる」心理には多様性があるのかも。
例示した写真は最近何度か紹介している
オホーツクの遺跡住居ですが、こうした自然のなかの
単純な幾何形体がそのたたずまいだけで存在感が強く際だっていた。
はじめて来ているのに「よく帰ってきたな」というメッセージが
わたしの感覚ではまことに強く感じられた。
また、去るときにも「またいつか帰って来いよ」と言われたと感じた。
そういう意味で、人類のDNAに刷り込まれたような「コード」が
あるようにも思えてならない。
家の「既視体験」的な部分に、そういうヒントが隠されているのでは。
お盆休暇のまっ盛り。
帰省ラッシュということで、各地から高速道路の渋滞情報。
こういう集団的帰巣本能って、やはり人間の基本的文化なのでしょう。
家のそういうメンタル的性能、奥が深いけれど探究したいですね。
Posted on 8月 11th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング | No Comments »
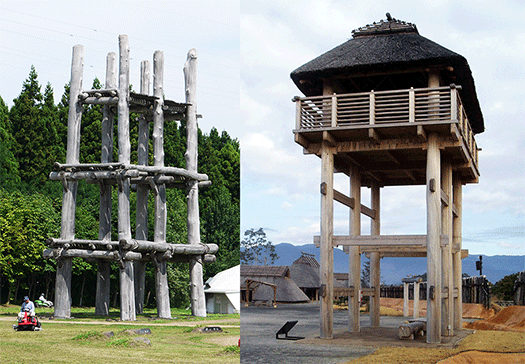

人類が洞窟住居とか、移動狩猟生活でのキャンプ生活から
定住的なライフスタイルを採用し始めたのは、
日本列島での縄文期というのが最古層ではと思っています。
だいたい16,000年前というように言われているようです。
では定住を始めるのにどういう住居に住んでいたかと言えば、
それは当然竪穴住居だったのでしょう。
地面に穴を掘って、その地域の年平均気温程度の室温確保が可能な
地熱利用できる深度まで掘り下げた。
その上で自然環境から得られるもっとも身近な素材として木を切って
屋根材として、あるいは柱材として利用しようと考えた。
そのときに、それらの木を「組み合わせる」技法、
いわゆる「木組み」について、相当研究開発したに違いない。
木を利用する動機としては、舟を作ることが先行したのでしょうが、
その技術はやがて建築に援用されるようになった。
船大工と家大工技術は相互に影響し合いながら人類発展を支えた。
この「木組み」技術について、どのような進化過程があったのか、
かねてから深い興味を持っております。
写真は、三内丸山(左)と吉野ヶ里(右)の
望楼建築とおぼしき建物を比較対照させたものです。
時代的には縄文と弥生の社会の技術の相違、進化ぶりですね。
高さ的にはほぼ同様程度と措定されているようです。
柱の数はどちらも6本となっていますね。
たぶん遺跡に残されていた柱の穴、その大きさと深さ,間隔、数など
情報を統合させて建築として復元したものだろうと思います。
年代的には三内丸山の方は5,000年前というように情報があった。
一方の吉野ヶ里は3世紀ころに最盛期を迎える遺跡ということなので、
いまから1,800年前ころを想定しているようです。
下の写真は両方の建築の「木組み」接合部の拡大写真。
縄文の方はつる性植物と思われるロープが利用され,一部では
斜めに柱に「受け木材」が付けられてそこに横架材が乗っている。
一方、弥生の吉野ヶ里では、
明確に柱に通し穴を貫通させた部位に、横架材が挿入されている。
いわゆる仕口の技術が明瞭にあらわれている。
このあたりは、重要な部分なので復元に当たっては建築史的な検証が
なされたうえで、こうした技術仕様に間違いないとされるのでしょう。
一昨日紹介した今から1,500年前ころの北海道オホーツク遺跡では
つる性植物によるロープ架構が措定されていました。
先述の船大工と家大工の系統分化もあって、
たとえば船大工の世界では、当初の丸木舟からさらに大型化のために
当然、防水を兼ねたしっかりとした「木組み」技術は追求されただろう。
想像としてはそういう技術開発の必然性は舟の方が先行して
やがてその技術が家大工の方に伝播していったのではないか。
それと、そのように精巧に仕口を造作するには鉄の道具革命も
あいまって進行しただろうと思われるのですね。
この木組みの進化物語、深く興味をそそられています。
Posted on 8月 10th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »


北海道内の人跡、遺跡を訪ね歩くと、
あんまり都市化されていないので、
自然のなかをさまよい歩くといった経験をよくする。
写真はきのう紹介した北海道オホーツク海岸側の標津の
オホーツク文化遺跡・カリカリウス遺跡にいたる道周辺の様子。
この一帯は、古代からの人跡が絶えない地域のようで、
たくさんの遺跡が集中する地域です。
地元標津町HPには、以下のような記述。
〜標津遺跡群は、国指定史跡である伊茶仁カリカリウス遺跡、
古道遺跡、三本木遺跡の3つの遺跡と、伊茶仁川沿いに残された
国指定級の遺跡群から成っている。標津遺跡群の最大の特徴は、
現在の地表面から数千年も昔の竪穴住居跡が窪みとして確認でき、
しかもその数が日本最大の規模を誇ることである。
現在、同様の遺跡である北見市常呂遺跡群と共に、
「北海道東部の窪みで残る大規模竪穴住居跡群」として
世界遺産候補に位置づけられている。〜引用終わり。
ということなのですが、このカリカリウス遺跡に向かうには、
周辺の国道に接道している標津町歴史民俗資料館駐車場からも
約1kmくらいは「散策」していくことになります。
周辺にはクマの出没もよく報じられるので、おっかなびっくりの道。
マジでラジオなどの音を発生させながら歩きたくなる(笑)。
昨日から札幌では南区の住宅街に9時間以上、クマさんが徘徊した。
大自然と共生する北海道はなかなかたいへんなのであります。
でもまぁ、無事に遭遇せず帰還できたのですが、
その道すがら、そういう決死の覚悟とはうらはらに、
ごらんのような「湿原」らしい光景が木道上から目に飛び込んでくる。
ただし、1枚目の写真のなかには「ルピナス」の群生。
このルピナスは明治以降にヨーロッパから移植されたもので、
その後の150年で野生化して、ここまで生息域を広げている。
北海道の気候風土がこの植物には「新天地」だったのでしょう。
そういう意味では西洋から来た「屯田兵」みたいな存在か。
遺跡探検のもうひとつの楽しみは、こんな自然との遭遇もある次第。
幻想的な湿原風景、かなりオススメです。
Posted on 8月 9th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究 | No Comments »


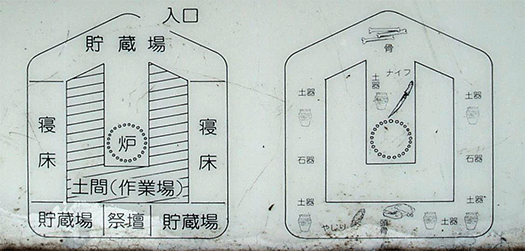
みなさんは「オホーツク文化(人)」って、ご存知でしょうか?
たぶん北海道に住んでいて考古学に興味のある人くらいしか、
知識を持っているヒトはいないのではないかと思います。
日本列島にはさまざまな人々が去来した。
最新の核DNA解析を信じれば渡来の波はおおむね3波に分かれる。
縄文のひとびとが2万年−4万年前ころに渡来して基層を形成した。
きわめて人類古層のアジア展開人種のDNAとされているそうです。
かれらが旧石器の様式文化も遺跡に遺しながらこの列島に姿を現し、
15.000年前くらいからは縄文文化を形成した。
それまでのキャンプ移動・狩猟中心から、定住的な漁撈+自然採集が生業になった。
その後、第2波の渡来民は縄文の末期で、『海の民』だった可能性があり、
日本語の祖語をもたらした人たちではないかとされる。
そして第3波は弥生時代以降。
生産手段としての本格的「農耕社会」の集団的移住。
さらに歴史年代に白村江の敗戦(663年)の結果、朝鮮半島の国家であった、
百済からの集団移住が最後の3波目を締めくくったとされる。
こういった世界各地からの「渡来」があり、婚姻などのブレンドがあって、
基本的な民族形成がされた、という説が有力とされてきている。
<国立遺伝学研究所・斎藤成也教授の説に準拠しました>
で、このオホーツク文化人というのは縄文人のDNAを色濃く残している
アイヌ民族での混血に関わるミニ「渡来」のようで、
北東アジア・アムール川流域地帯から、主に大型の海獣を獲物として
追ってきて北海道の東部、オホーツク沿岸地域に定住した人々。
特徴的にはクマのアタマを神聖祭器として祀る風習を持っていた。
そのひとびとの居住痕跡を発見し復元住居としたのがこの家。
わたし自身の「古民家」探究のなかでもかなりインパクトのあった住居。
平安期日本の宮廷社会では海豹の皮革が貴族の女性の身を飾ったし、
鷲の羽根が、貴族の装身具として最高級素材とされたそうです。
そうした素材は、オホーツク文化人の狩猟生活の産物であり、
奥州藤原氏などの交易中継を経て、日本国家と交易を行っていた。
やがて、クマの神聖祭器風習をアイヌ民族に残して混血同化していったと。
そういうかれらの「住居」なのであります。
どなたが復元設計に当たられたかは知りませんが、たぶん北海道の
古建築について知識を持った建築の先生が関与されたに違いありません。
現地に置かれている説明資料によると
「約1,000年前のオホーツク文化の竪穴住居を二つ復元しました。
手掛かりは柱や炉の位置、焼け残った柱や壁の材料だけで、
屋根や柱の組み方は想像した部分が多いのです。この時代の人々の
家を作る道具は、鉄製の斧やナイフのほかは、木や骨の道具でした。
ですから家を作るのに使う木の性質や特徴をよく知っていて、
加工する技術が高かったと言えるでしょう。」と書かれています。
そして「材料」として以下の記載がある。
「壁〜板143枚。
柱や母屋材〜太い丸太55本。細い丸太60本。
結束材〜ブドウつる 450m、シナ縄 600m
屋根材〜白樺の樹皮 300枚(長さ3m径30cm300本)
床材〜角6本 板22枚」
このインテリア写真は2枚の写真を接合合成したもの。引きが取れず2枚で撮影。
一部不整合部分がありますが、カメラマンの力量足らずです、ご容赦を(笑)。
内部はごらんの通りですが、炉の周りには「ヒカリゴケ」が異彩を放つ。
Wikiによると<1科1属1種の原始的かつ貴重なコケ植物。
その名が示すように洞窟のような暗所においては金緑色(エメラルド色)に光る。>
ということで、素晴らしい装飾効果を見せてくれている。
わたしの取材経験でもっとも感動したインテリアの演出装置。
まるで千年の時を超えて生物痕跡として、住んでいたひとたちからの
メッセージのようにその光彩がこちらに伝わってきた。
初めて訪問してからもう12年が経過していますが、
いまもときどき熱に浮かされるように思い出す住宅です。
Posted on 8月 8th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »

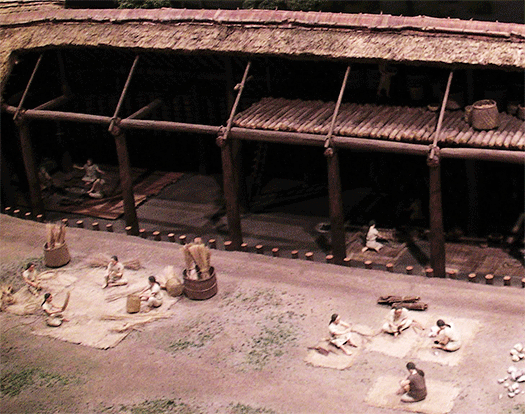
先日、社内スタッフのお父さんの葬儀に参列させていただいた。
わたしよりも8−9歳年上ということですが、
イマドキにしてみるとやや若い年齢での死と思えた。
その経歴などを聞きながら、自分自身の経験とも共鳴するような事跡が
語られていくウチに、ふと、重ね合わせて考える瞬間もあった。
生きることをどう使って、役に立つ、なにを残せるのかと考えるようになる。
まぁいわば、ライフワークということへの思い。
人間というのは現代では、そこそこの教育を受けることができる。
教育というのは、どういう「意義」があるかと考えれば
近代の資本主義社会の中で、それを発展させるために
「人材」として働いて生きていくための基盤を構成するものでしょう。
そしてそのなかで、どういう分野を選択するのかは、
各個人がそれぞれ自由に選択していくように社会が構成されている。
人類発展の現段階だと思いますが、かなり進化してきたと思える。
わたしの場合で言えば、一定の教育を受けてメディア関係の周辺で
仕事を選択して、とくに「住」の情報に特化して生きてきた。
そういう経験を、どのように自分で総括していくのか、
そんな思いがすこしづつ芽生えてきているように思われます。
写真は、千葉県佐倉市にある「国立歴史民俗博物館」での展示詳細ジオラマ。
住という部分で日本人はどう生きてきたのか、暮らしてきたのか
その始原に近いようなものとして、青森県青森市の三内丸山遺跡がある。
このジオラマは、その中心施設・大型の竪穴建築での「暮らしよう」を
再現するべく構成されたものでした。
わたし自身は学生時代からもっとも歴史には興味を持ってきた。
仕事としては情報・メディア関係を志向して住関連にシフトして
そこで、人間のくらしのありようを「伝える」ことに集中してきた。
たまたま、日本最高の寒冷地である北海道に生まれたので、
そういう気候克服技術進化については、カラダで分かる部分も持っている。
その手法、スタイルで、歴史についてもついつい、
「あなたはどう暮らしていますか?シアワセですか(笑)」という問いを仕掛ける。
いろいろな歴史的建築・住居などを実体験しながら、
いまはもう死んだひとたちに「取材」しているように思うのです。
まぁ、自分がこれから、なにごとかをまとめていくとすれば、
こういった領域が、いちばんふさわしいと言うことを確信しています。
この15,000年前ともいわれる三内丸山の縄文のひとびとの生活は
いろいろな研究者のみなさんの解析で、相当に詳らかになってきている。
このジオラマ自体、そういう研究成果そのものでしょう。
大型住居の屋根は自然素材で「編む」ように仕上げられる茅葺き。
そういう技術が確立しているとすれば、むしろや衣類もまた、
その技術援用から可能になっているだろう。
農業とは言わずとも、栽培的な営みに近い営為は自然に想定できる。
ジオラマの一部、2階として利用している箇所には
植物性食料を保存させるような工夫も見ることができる。
・・・このブログではこれまでもそういうテーマが大きい部分ですが
こうした領域について、もうちょっと目的的に「取材」を進めてみたい。
Posted on 8月 7th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅取材&ウラ話, 歴史探訪 | No Comments »

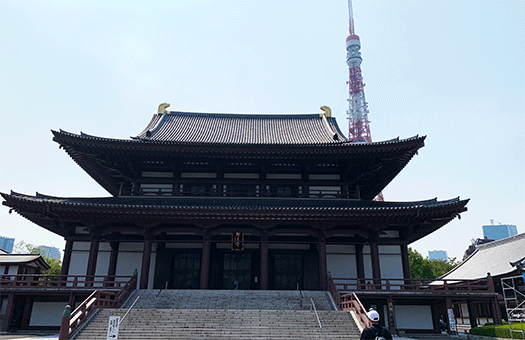
江戸期における芝増上寺というのは、
一種の国家施設的な存在であって、いまの皇居からも4kmほどの近さに
広大な境内地を構えて存続してきている。
けれども、この寺院は東京空襲で焼かれて、
江戸期の貴重な工芸的建築であった、徳川秀忠霊廟「台徳院殿霊廟」も
消失されたということだそうです。
しかし、実はこの工芸建築の1/10模型が明治期にイギリス王室に
プレゼントされていて、それが近年里帰りして増上寺の「大殿」地下の宝物展示室にある。
江戸期の建築というと、日光東照宮が想起されますが、
その東照宮に先行して建てられた幕府の威信を賭けた工芸建築だということで、
見学して参りました。
こちらは、写真撮影などは許諾されていませんので、写真は増上寺「大殿」。
先日の東京出張の折、アポの時間合間に見学して来ました。
この模型は100年前にロンドンで開かれた国際博覧会に出展されたそうです。
この模型は、しかしイギリスでは保守管理する技術者も存在せず、
展示することもできずに長年倉庫に留め置かれていたということ。
今回里帰りしたのは、英王室から長期にわたって貸与された形式を取っているそうです。
プレゼントされたものを「返す」というのは失礼に当たるという考えでしょう。
コンパクトな模型とは言え、作りはまことに工芸品そのもの。
東照宮のような極彩色で曼荼羅の世界が再現されていました。
そもそもが御霊屋という一種の墓であるので、
建築でありながら、各部位はまるで工芸品のように仕上げられています。
内部でも無数の「組み物」が幻想的、宗教的な空間を作り上げています。
江戸幕府開設時期というのは、戦国期の活発な城郭建築が
全国的に終息することになって、建築不況に突入したのでしょうが、
一方で江戸幕府が武家政権として成立し、新開地・江戸の
まちづくりがあらたな「建築需要」として盛り上がっていたのでしょう。
そういうなかでも、もっとも手間暇の掛かる建築として
最上級の技術者が動員されていた様子が、展示からうかがうことが出来ます。
左甚五郎などの名工たちが、活躍の場を与えられた。
一方で、江戸に屋敷地を与えられた大名たちも、屋敷を造営し、
それぞれ庭園土木事業も活発に行った。
それまで戦争に傾けられていた財力が、こういった建築に資金が注がれていった。
大工という存在は最高に稼げる職業として人材を集めていったのでしょう。
この工芸建築の随所から、そうした時代の豪勢な職人仕事のありようが漂ってくる。
この時代の建築のありよう、その活況ぶりを追体験してみたいと思いますね。
まぁ、個人的にはこういうデコラティブな装飾性にはやや・・・(笑)
でも、繊細な工芸仕事にはやはり圧倒されます。
<撮影不可だったので、写真は同様式の「日光東照宮・陽明門」です>
Posted on 8月 6th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング | No Comments »

韓国との関係が非常に難しい状況になっていますね。
当面の間は好転するようなことはないように思います。
こういう時期には、不測の軍事的衝突のようなことに慎重に注意すべきでしょう。
対中国やロシア、北朝鮮についてはさまざまな「シミュレーション」が用意され
いわば「危機管理」のひな形、定型化した対応があるそうですが、
韓国との間ではそのようなことを想定していないとされる。
<ちなみに、今この状況の中で、ノー天気に「芸術祭だ」と言って
公費を使ったイベントを仕掛けて炎上させている自治体があるようですが、
活動家的な「芸術監督」は別にしても、知事さんの感覚を疑ってしまう。>
こういう時期、とくに国家間のことなので、緊張はあり得るけれど、
そうであるほどに、注意深く「管理コントロール」する必要があるでしょう。
務めて冷静な世論になるようにキモに銘じていなければならない。
ただ、歴史を見ていると、
こういう国際情勢感覚は日本が置かれた地政学的な位置から、
ながくあり続けてきたというのは自明ですね。
江戸の「鎖国」は、東アジアにおける一種の平和戦略としても機能していたのでしょう。
東アジア世界ではながく中国との関係が基本的国際秩序であり、
朝鮮半島国家にしてみれば、日本は「夷狄」的に見えるのでしょう。
そういった国際秩序に対して、日本は「脱亜」の方法として
最低限の国際関係にしたいということで鎖国していたのではないか。
非常にすぐれた平和的外交方針だった。
幸いにして、海を隔てていることがこうした方針を可能にしたのでしょう。
最近の日本の対韓国の考え方で
「ていねいに無視する」という小野寺前防衛大臣の考え方があるけれど、
そこには江戸期の鎖国政策的な色合いが強く感じられる。
「鎖国」には対外的緊張をあおるような側面は見出しにくく、
相手側にも、基本的には平和的な姿勢は十分に伝わるのだと思われる。
国としては嫌われていることは知った上で、平和的に近隣でいるためには、
断絶ではなく、鎖国という「迷惑を掛けない」という姿勢の方がいいのでは。
「善隣友好」ではなく「善隣鎖国」という考え方。
国民間や経済の人的往来とか交流は大いに行うことは地政学的に当然で、
あくまでも政府間での関係について、ということ。
この「鎖国」的な対応の仕方というのはあくまで「対韓国」だけの考え方で、
世界との関係についてはまったくこれまで同様ということです。
心構えというか、国民感情的にヒートアップしないためですね。
乞われれば対応するけれど、けっして深入りはしないというように。
国としての対韓国外交方針として、鎖国的に対応すべきではという次第。
<写真は国立博物館で展示され撮影許諾の横山光輝さんの「三国志」原画。>
Posted on 8月 5th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 状況・政治への発言 | No Comments »
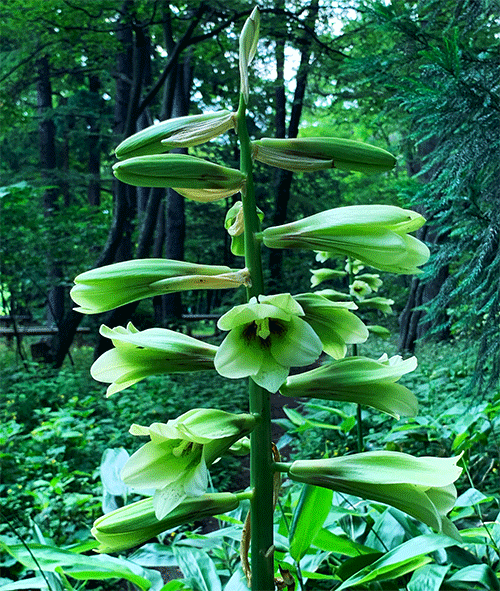
わたしの好きなBS-NHKの番組に「英雄たちの選択」があります。
日本史を題材に、歴史家の磯田道史さんがMCを勤め
歴史周辺関係のゲストたちと面白く日本民族の深層に迫ってくれる。
先週は「万葉集」についての特集でした。
万葉集の編纂は、奈良・聖武天皇の頃に開始された。
東アジア世界との活発な交流・戦争の時代であった天智天皇(大王)の時代から
白村江の敗戦を経験し、その後朝鮮半島から百済の国家的流入があって、
やがて中国の王権との平和共存が実現していって、
本格的な「国家」が樹立されていった時代なのだと思います。
天智の弟である天武がはじめて「天皇」の即位して、
中国王朝との外交を展開しそれまでの倭国から「日本」に国号を
国際的に認めさせ変更させたとされている。
たぶんこの間の戦争から国号変更に至る過程は、日本の根幹形成期。
そういう時代背景の中で万葉集は成立していった。
書き言葉はまだ漢字しかなくて、それを「万葉かな」ということで、
それまでの「やまとことば」に一音ずつ漢字を「当てて」いた。
明治の初め頃にも、日本はあらたな文明との遭遇から
日本語の創出をしなければならなかったけれど、
ちょうど、この万葉集編纂のころも同様の社会変革時期だったのだと。
日本ではこの時期から身分を超えて社会全体で
言の葉をつかって、万葉な多様なひとびとの感じたことなどが
残され、それを現代人でも「追体験」することができる。
日本語という独自の民族的文化基盤を獲得していった。
漢字という世界標準の言語が導入され、文章博士という存在が
日本全国に派遣されて、普及啓蒙されていくと同時に、
それを使って、この列島で暮らしていたひとびとの心象が表現されていった。
やまとことば、という文字を持たない言語が、
このように表現されるようになった。
そのことによってわれわれと同じような人間感情をもっていたことが、
明瞭に後世までそのことを感受することができる。
そこからでも1500年程度の「文化蓄積」が可能な基盤が形成された。
いまや、その存続時間は世界有数の国家社会。
基盤としての「日本語」というもののありがたさ、
そのために苦闘した多くの先人たちの営為を大いに思わされますね。
Posted on 8月 4th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »
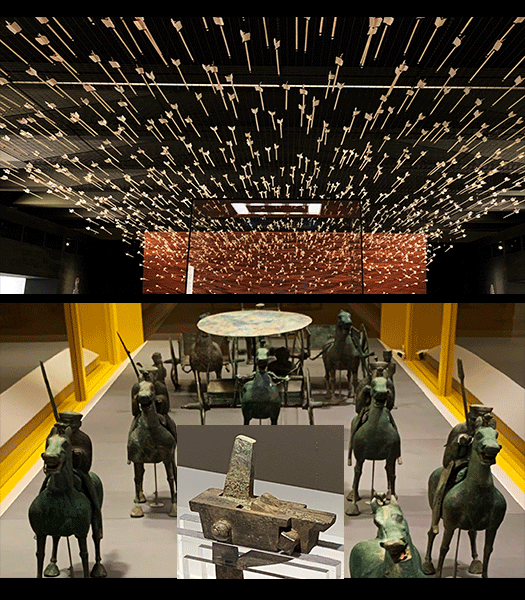
本日は、住宅ネタ休日。三国志世界の戦争ネタ。
悲しいかな戦争は、人類の進化と常に随伴して「発展」してきた。
他人を殺すという目的がなによりも権力獲得の最有力手段であり
その目的完遂のために、兵器は進化してきた。
中国は、人口集積・文化発展において日本にはるかに先行して
この三国時代には、人口760万人程度なのに、
その戦争スケールでは、常に十数万という多数が参加して殺し合いを行っている。
そういうなかでも「赤壁」はその後、魏・蜀・呉の3国が鼎立する
最大の契機になった揚子江を舞台とした大水上戦争としてのクライマックス。
この水上戦では、矢いくさが多様に展開したとされる。
その「花形」になっていたのが、ほぼ自動化した矢の射出装置「弩弓」。
今回の国立博物館展示でも、海上の1/4を独占して
写真上のような矢戦の様子が天井一杯に展開していた(笑)。
まことにわかりやすい展示展開。
みなさん「超弩級」というコトバは普通の形容詞になっている。
たぶん、この弩は中国大陸ではどんどん進化して
その後の鎌倉期の元寇でも主力兵器となっていたのでしょう。
弩級という言葉が根付いたのは、日本では少人数・小規模の局地戦争が多かったので
弩はあまり発展しなかったのに対して、アジア征服戦を戦っていた元軍は
このような大型射出装置が発展していたので、日本側が悩まされたと言われる。
諸葛孔明が、矢をたくさん収集するのに敵陣近くまで
草屋根にした高速船を浸入させて、屋根にたくさんの矢を射させて
高速全力で引き返して、戦利品として矢を一晩で得たという逸話がある。
いかにも大陸中国での戦争営為のスケールを大きさが
三国志世界の真骨頂なのでしょう。
しかしわたし的にはどうも戦争ばっかりやっている描写は、登場人物も多すぎて
いちいち名前を覚えて感情移入するのがメンドクなったりもした(笑)。
やっぱり戦争は、桶狭間のような電撃戦とか、
関ヶ原のような戦場以外で雌雄が決しているような政治陰謀の世界の方が
ニッポン人的には、近しい感じが否めません(笑)。
PS:
どうも「弩級」というコトバについては「弩」は関係なく、
以下のようなことがらがコトバを生んだ経緯だというご意見が寄せられました。
わたしの「意見」も添えさせていただいて、書き加えます。
〜
Shigeru Narabe 弩級、超弩級は、1906年進水の英国の戦艦ドレッドノート
(HMS Dreadnought)から来ています。
https://ja.wikipedia.org/…/%E5%BC%A9%E7%B4%9A%E6%88%A6…
三木 奎吾
Shigeru Narabeさん,その通りのようですね。ただ、どうも自分的には
「弩」の方のイメージが強かった。司馬遼太郎の記述でも、兵器としての「弩」は
かなり日本人と鎌倉武士たちに強烈な体験を残したと書かれていた記憶がある。
この戦艦が登場したときに、ドレッドノートのアタマの「ド」に対して日本語として
漢字の「弩」を当てたのにはどういった整合性、必然性があったのか。
そこが知りたいと思っています・・・。
〜以上。
Posted on 8月 3rd, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 歴史探訪 | No Comments »