住宅というのは、大きな意味では「どうやって日射制御環境を作るか」だともいえる。
温暖地での住宅伝統として、過剰な夏期日射を抑えることが
基本的な「性能要件」とされ、冬期の寒さについては「耐え忍ぶ」ことが
日本人の生活文化には色濃く刻印された。
そういう基本的な住宅文化のなかで、紙による障子文化は
基本的にはガラスが住宅の窓に嵌められる前まで「光の導入」が
大きな役割で、その装着結果として光が微妙にコントロールされたのでしょう。
畳という芸術的な繊維装置とあいまって、日本人の精神文化に
たぶん微妙・繊細というような感受性を大きく植え付けたのだろうと思っています。
紙越しに伝わってくる光は微妙なアンジュレーションを見せて、
境目のあいまいなあわい光というものへの独特の気分を演出していた。
そういう窓の障子が、ガラスが窓枠に嵌め込まれるようになって、
それでも「内窓」「建具」という装置として延命してきたのは、
機能を超えた感受性装置という側面が大きかったのだろうと思います。
高断熱高気密の住宅技術は、基本的に「気密性」を高める技術。
ガラスがまずは外部建具としては前提とされ、
さらにペアガラスやトリプルガラス、アルゴンガス封入といった性能進化が図られた。
きのうもご紹介したTAO建築設計・川村弥恵子さんの事務所建築では
なだらかに敷地高低に添った屋根傾斜が掛かっているので
主室の、工場出荷可能の限度一杯という高さの大きな高性能ペアガラスの窓に対して
その「日射コントロール装置」を考えるとき、
ロールブラインドという選択がありえなかった。
傾斜屋根なりの窓ガラスなので、上端部分に隙間が発生する。
一方であらたな素材や建具への強い関心もある。
そういうなかで、この写真のような「障子風」の建具が選択された。
聞くと、四国で「りくう」というスタジオを主宰されている紙漉きアーティスト
佐藤友佳理さんの作品を川村さん側で建具に仕立てたもの。
一種微妙な、一期一会的な漉き「ムラ」を建具として実現している。
仕上がった独特の建具は外部から見れば、かなりのブラインド効果を持ち、
室内側からは外光の制御が非常に繊細に可能になっている。
「見ようと思えば外部を見ることができるけれど」
それこそ「あわい外部とのコミュニケーション」が可能になっている。
そうか、障子が進化してきているのだ、というような気付きに至る。
ランダムな一期一会的な光の乱反射、制御が同時に楽しめる。
ひとつの絵のようなオブジェ感もたのしい。
日本人の「窓辺」感覚にまたオモシロい体験を
もたらしてくれる建具ではないかと、非常に感銘を受けた次第です。
Posted on 1月 11th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 住宅取材&ウラ話


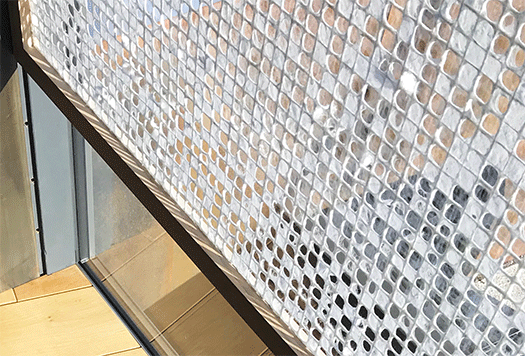






コメントを投稿
「※誹謗中傷や、悪意のある書き込み、営利目的などのコメントを防ぐために、投稿された全てのコメントは一時的に保留されますのでご了承ください。」
You must be logged in to post a comment.