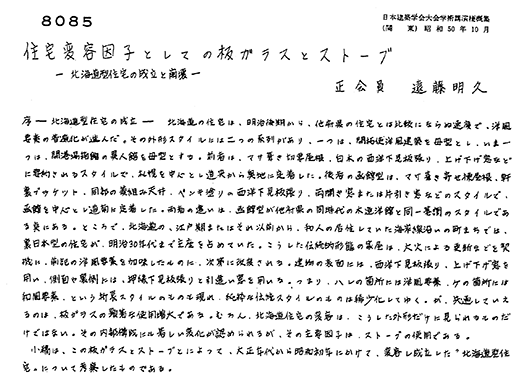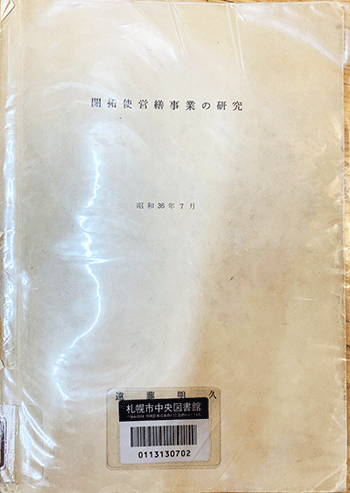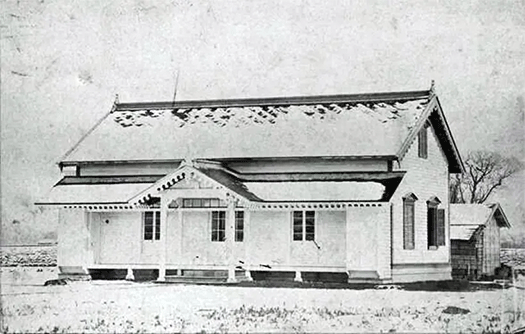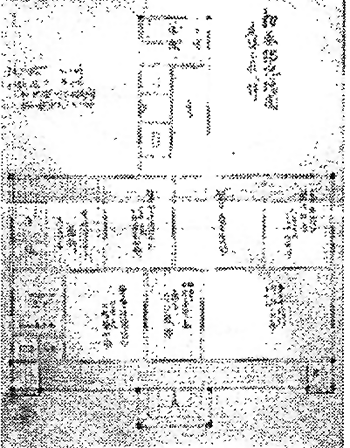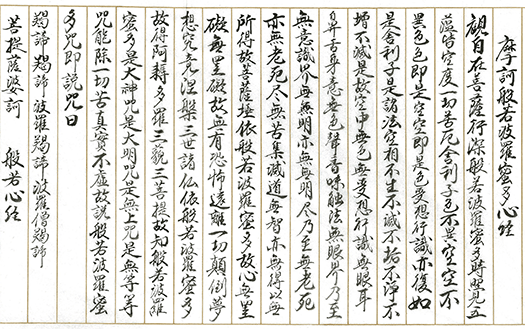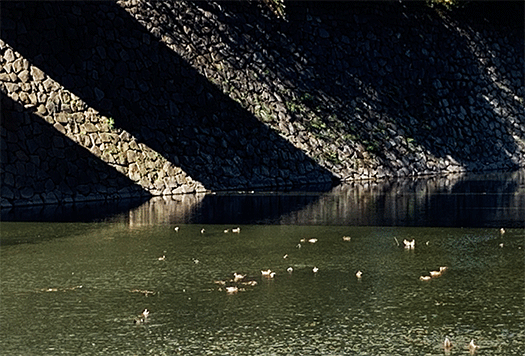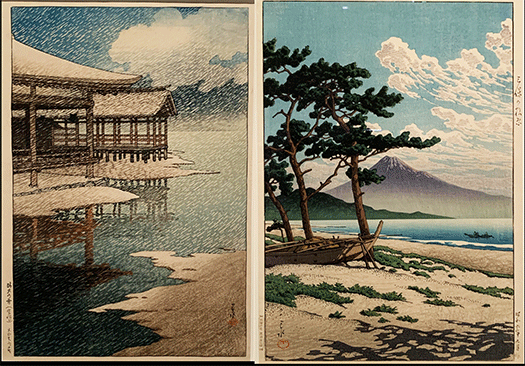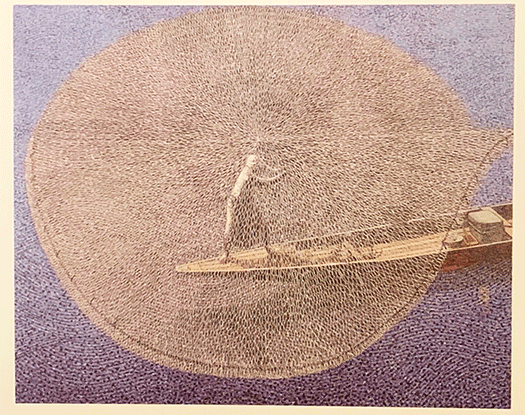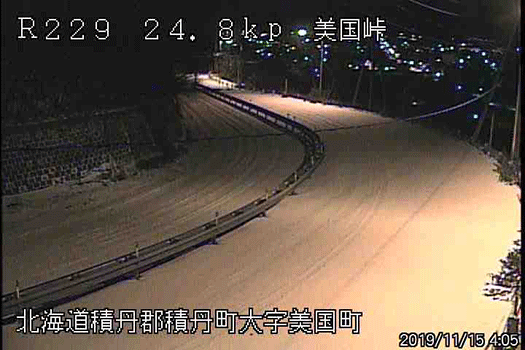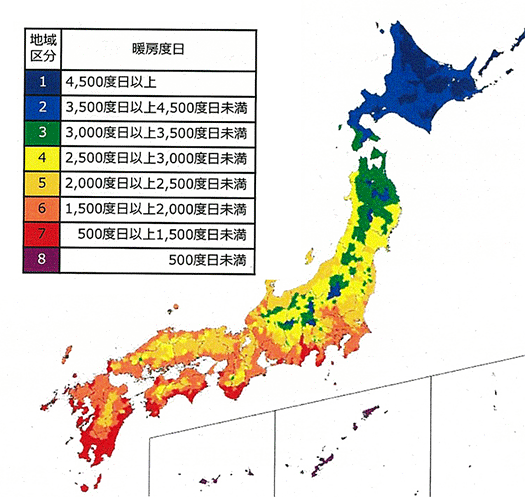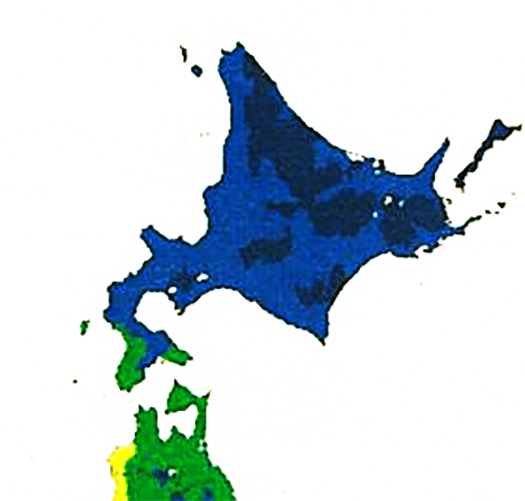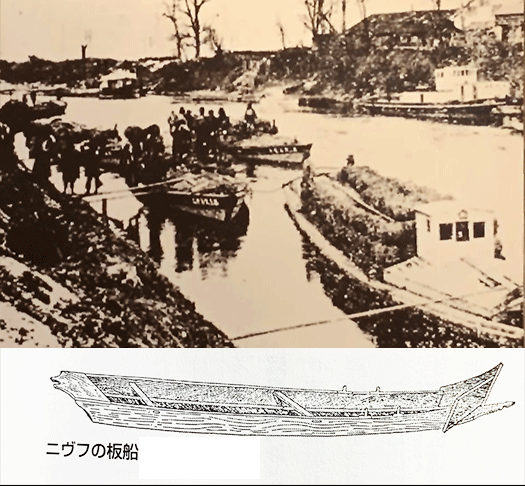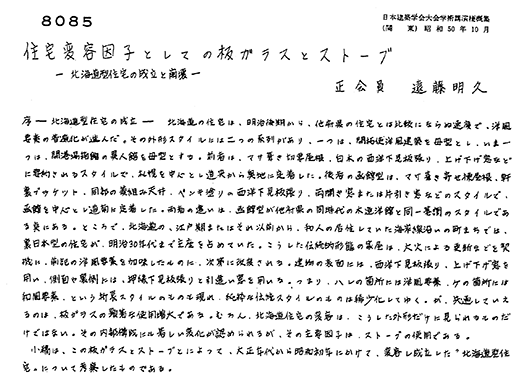
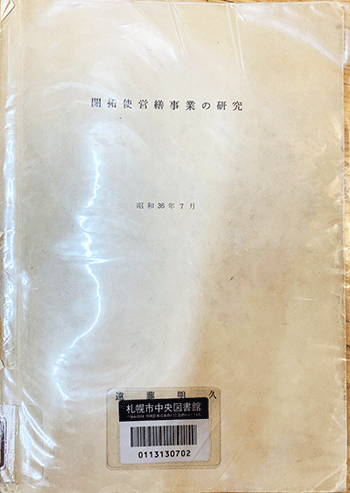
人間、継続してなにかに興味を持ち続けると
いろいろな助力を得られるものだと思います。
わたしは北海道に生まれて住宅の雑誌を発行し続けてきた人間です。
必然的に「高断熱高気密住宅」という地域住宅文化のハブを意図してきた。
いまでは東北や関西といった地域でも発行して
そういう家づくりを志向する運動のハブ機能も果たしたいと活動してきた。
そういう流れの中で、北海道が体験し希求して、突き詰めてきた
「高断熱高気密住宅」技術伝承のコアを探究したいとも考えます。
たまたまブログを書き続けているので、その1シリーズとして
「北海道住宅始原への旅」を探究してきています。
大学は文系でメディアとかコミュニケーションの世界で生きてきた。
住宅建築は、雑誌を作ってくる中で意図的に出会った領域。
そういうことなので学究のみなさんとは知り合いではあるけれど
自分自身には建築を学んだ蓄積はない。
あくまでも人間・暮らしの目線で住宅を見てきています。
そんな無謀な試みを続けていると助力を申し出てくれる方もいる。
で、教えていただきめぐり会ったのが遠藤明久先生の著作群。
とくに「開拓使営繕事業の研究」という労作は探し求めても入手不可能と
思っていました。古書店を巡り歩く時間的ゆとりはないし
Amazonなどで検索してもヒットすることはない。
かろうじて大学4校図書館と札幌中央図書館には1冊だけある。
ということで、きのうようやくこの本とめぐり会うことが出来た。
しかも、コピーもすることが可能ということで、
先生の労作本文内容を入手することが出来た次第です。
これで明治初年からの北海道の住宅建築探究の基礎資料ができた。
と喜んでいたら、今度は北総研の高倉さんからメールで
くだんの遠藤先生の「肉筆」の論文PDFが送られてきたのです。
メールの本文には「三木さんの問に対して天国の遠藤先生からのお手紙」
というように書かれていて、まことに感無量。
遠藤明久先生の主な経歴は以下。
1915年 北海道小樽市生まれ
1934年 札幌工業高校建築科卒。函館市復興局入庁。
1945年 北海道庁勤務
1968年 札幌五輪冬季大会組織委員会施設部計画課長
1972年 「開拓使物産売捌所の研究」で東大から工学博士
1972年 北海道工業大学教授。
〜北海道文化賞、小樽市歴史的建造物保全に関わる。ほか受賞多数。〜
1995年 逝去
わたしはまったく知遇を得ておりませんが、
はるかに学ばせていただき、探究を続けたいと思います。感謝。
Posted on 11月 22nd, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »

北海道住宅の最初期、というか明治政府による「開拓使」設置からの
北海道開拓殖民において決定的な要素領域であった、
「住環境」についての始原を探ってみようという企画を進めています。
もちろん、前史はかなり遡れるのですが、
今日のライフスタイルに直接つながる「住文化」を
遺されている多くの資料を目的的に活用して、活写しておきたい。
とくに高断熱高気密という日本の住宅を革命しつつあることがらが
どのようにスタートしてきたのか、明治初年から
整理整頓してみようと考えている次第です。
開拓使は北海道開拓の本府として札幌を選択して、
そこに日本民族による寒冷気候を克服した「五州第一の」都を
造営しようと企てた。(判官・島義勇)
一部のアイヌのコタンを除けば人跡がほとんど見られなかった
札幌に旺盛に都市を建設し、住居を建て続けてきた。
明治初年であり、脱亜入欧の気風が強く洋式をもって範とする考えが貫かれた。
この写真の「勅奏邸」は開拓使の現地トップがその建築でも範を垂れる
そういう意味を持たせて建設されたに相違ない建築。
この当時「ガラス邸」と通称されていた建物にいちばんふさわしい。
その鮮明な写真が、北大のデータベースに保存されていた。
上の写真は、それの前面の縁・デッキテラスに面した正面側の「窓」を
クローズアップさせたものです。
右手には「雨戸」などを収蔵する「戸袋」もありますが、
窓自体を見ると、四角く桟で区切られた様子が確認できる。
ここに「ガラス」が嵌められていたことは想像に難くない。
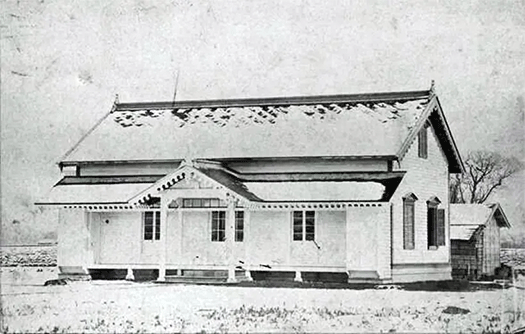
通称ガラス邸という記載は明治5年の「御用火事」を伝える
資料などで「ガラス邸前から」という記述が見られているので、
それ以前に建築されていることがあきらか。
天皇の機関である「開拓使」の現地駐在官トップの邸宅なので
建築の動機に於いては最初期建築として建てられた可能性が高い。
その建築においてその後の札幌都市で一貫して追及された
「洋風建築デザイン」の嚆矢として取り組まれたと思われます。
そういう意味で「北海道住宅始原の家」と称して格式的にもふさわしい。

こちらの写真は右手側壁面の様子。
戸袋や外開きの木の被覆扉もみられる。
外壁は下見板張りが採用され、その後の北海道の屯田兵屋などの
デザインがここですでに基本的に採用されている。
ただし、明治初年段階では建材としてのガラスは輸入であるのか
国産化されていたのか不明。
いずれにせよ、高価であったことは想像に難くなく、
そういう建材が周囲を睥睨するように使われ「範とすべし」と
これみよがしに建てられていたことが容易に想像される。
そういう展示効果も狙っていただろうけれど
「ガラス邸」という通称名から、透明な窓というものへのオドロキが
意図されていたのだろうと考えられる。
どうもわたしのこの「始原期の探究」からガラス窓というものの
果たした役割がクローズアップされてきます。
洋風住宅の導入ということが日本の住宅の革新であり、
住宅性能の追求が、開拓使の住宅政策の基本に存在していたと思えるのです。
今日で言えば1枚ガラスの熱的に貧相なガラス窓ですが、
それまでの障子と雨戸という「開口部」の常識からすれば、
気密、ということを日本人に意識させる効果をガラス窓は果たしていた。
このことが大きなテーマとして浮かんできたのであります。
追伸:ガラス邸の建築が判明しました。
建築史の碩学・遠藤明久先生の文献にこの建物に触れたくだりを発見。
建物としては「夕張通第壱号邸」という「和風建築」で明治5年4月に
札幌市北4条西1丁目に建てられた「官舎」。
で、当時はきわめて珍しい「ガラス嵌め込み」建具が縁側に
組み込まれていたとされる。それを展示公開していたとのことで、
多くの札幌在住者に「ガラス邸」という通称名で知られていたとのこと。
ついに疑問のひとつが解決いたしました。
本ブログで紹介の「勅奏邸」はやや完成年度が下がり
明治6年10月という記録もありました。訂正致します。
Posted on 11月 21st, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »

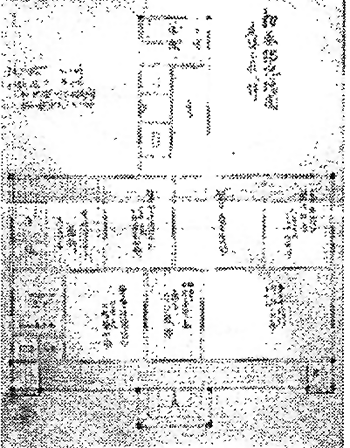
本日はしばらく書けなかった「北海道住宅始原の旅」シリーズです。
書けなかったのにはいろいろ忙しかったということもあるのですが、
特徴的な「住宅」ということで屯田兵屋とかを書き続けてきて
開拓使の長官邸、名前だけは記録に残っている「ガラス邸」について
さまざまに調査活動をしているのですが、なかなか進まないのであります。
岩村通俊や、その後の長官・黒田清隆などが札幌にいるときは
この建物を使ったに違いなく、また例の「御用火事」についての記録文でも
「ガラス邸前あたりから・・・」という一般固有名詞として
いわば「みんなが知っているあの建物」みたいに書かれている。
ところが、この建物がどういう建物だったか、記録が見えない。
北海道住宅始原の旅プロジェクトとしては、まことに画竜点睛を欠く。
「我流がいいところで、そんな画竜なんて」とヤジが飛んできそうですが(笑)
どうもココが気に掛かって仕方がないのです。
そういうわたしの悩みの理解者、建築研究者の高倉さんからヘルプで、
北海道の建築界の錚々たるみなさんが共同執筆されている
学術論文がありがたくも送られてきました。
「明治前期洋風住宅の平面計画の基本形に関する研究」というもので、
主査が駒木定正先生で、小林孝二・山之内裕一・中渡憲彦各氏が「委員」の論文。
そのなかに「勅奏邸」という、どうも胸騒ぎを憶える名の建物の情報。
勅奏というのは「① 天皇が仰せになることと、天皇に申し上げること。
② 〔「勅奏官」の略〕 天皇の文書を取り扱う役人。」ですから、
「開拓使」の長官なり代表者なりが利用する建物と比定させることにムリはない。
長官職は中央政権の閣僚なので北海道現地には常住せず、
基本は代行者が現地駐在なので、長官邸とせず勅奏邸とするのは理解出来る。
その論文に掲載された写真と図面を示してみたのですが、恐縮ですが
なにせPDFで圧縮された画像データの「復元」なので鮮明ではありません。
論文でのこの建物についての記述は要旨以下の通り。
「勅奏邸の建物の構成は主屋と背面の付属家からなり、主屋は切妻平入りで、
ファサードを左右対称として中央に玄関を据え、その両側を吹き放ちの縁とする。
縁に裳階状の庇と両端部に戸袋を設けているのは和風住宅の引用と推察される。」
(引用以上)・・・ということで、戸袋があるなら雨戸が仕込まれていた。
それは和風住宅仕様で、洋風建築のキー建材「ガラス」がイメージしにくい。
しかし、主題としての「洋風住宅」認識は下地にはある。
縁の中側に主屋居室があったワケで、その居室が半外である縁との仕切りに
ガラスの「窓建具」で区切られていたのでは、という想像は湧いてくるけれど、
そういった記録がまだ発見確認できない。
写真を見ると、縁越しに縦長の「窓」が見えている。
ここにガラスが嵌め込まれていたのではないか。
初期のガラス窓は障子建具代用の考えから「戸袋」も併設された?
新時代を感じさせる住宅建築としてのランドマークにガラスを利用。
だから「ガラス邸」という通称名が流布されたと睨んでいるのですが・・・。
どうもこれっぽくね、という私設「鑑定団」見解なんですが、
イマイチ、まだ決定打には至っていないかなぁというところ。ううむ。
どなたか「ガラス邸」について情報をお持ちの方、教えてください!
Posted on 11月 20th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »
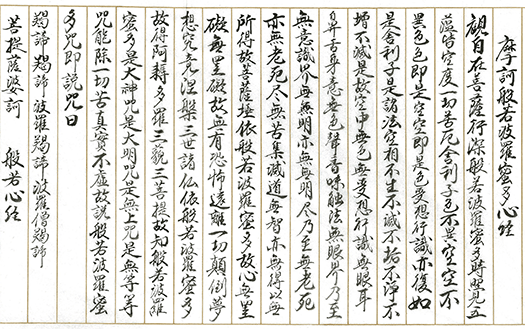
ことし96歳になる叔父が健在です。
大正12年・1923年生まれ。学校には16歳まで通ったことになる。
教育を受けたのは約10年間。
しかし、家族や学校からは厳しい教育を受けて育ったのだという。
教員免許を持って数年間は教壇にも立っていた長兄の叔父から
厳しく教育を受けたそうで、書をきちんと書けなければ、
鉄拳制裁を受けていたと語っている。
いまの偏差値教育とはまったく違う教育体系だったのだと思う。
「名は体を表し、書は人格を表す」というように教育を受けた時代。
書に向かう心構えにおいて、いまの人間とは根本が違う。
その叔父の書のもつ力に触れた兄が、その書を持って訪ねてきた。
書を写し撮って印刷し板に張って、さらにその板を彫刻して
掲額としたいのだという。そういう趣味作品が知友に好まれるそうだ。
デジタルデータにスキャンして、多用途に使えるよう長期保存させた。
その書の持っている力のようなものが自然とそういう気にさせるものか。
そういえばよく、明治や大正までの「エラい人」の書を掛け軸にする、
そういう床の間飾りを目にすることがある。
ご多分に漏れず、わたしもそういう趣向の好みには距離感があり、
そういう「エラい人」信仰のようなものに反発を感じていた。
総理大臣になった人物「だから」エラいというような価値感はヘンだと。
しかし最近の教師同士でのいじめごっこなどにあらわれる
「教育の荒廃」の極限形態のようなものを見させられると、
このような「書は人格を表す」というような教育的な価値感に
清々しさとリスペクトを強く感じさせられてならない。
同僚に対して暴力的いじめをふるうとかを普通の教師がやっている。
あまつさえ、いじめなのかふざけなのか、先輩教員たちが
新入教員たちに男女の交友を強制までもしていたという。
まさに腐りきっている現実があるが、いまだに「人権」とかに守られて
その名前すら公表されてもいないし「有給休暇」扱いなのだという。
そういった総体としての現代「教育」には絶望しか感じない。
実態としては教師の労働組合におもねった「教育委員会」という
ヌエのような存在が、日本の教育を根こそぎ腐らせているのではないか。
こどもの人格形成システムにおける無責任体制の積極的推進・・・。
まさかそこまで、と思う人間的堕落がシステムとして機能している。
ああいう「教師」がどういう「思想」をこどもに植え付けるのか、
考えるだに怖ろしいことが現実に行われてきている。
あれはまさに氷山の一角にしか過ぎないのだろう。おぞましい。
人間倫理というものは現代教育から絶滅したのか?
そういった狂乱する現代教育から見返してみると、
戦前期に鉄拳で叩き込まれた「人格を表す」ような書には、
やはり自然とつたわってくるモノがあると思えるようになって来た・・・。
Posted on 11月 19th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究, 状況・政治への発言 | No Comments »
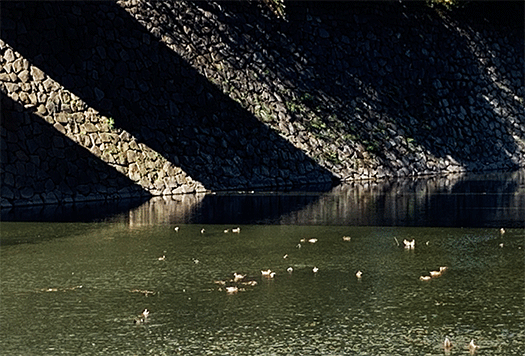
写真は大嘗祭の皇居・竹橋から見たお濠。
江戸という街は人工的に作られた都市。
マザーになった集落というのは、太田道灌という武家が
その前身を形作ったと言われているけれど、徳川家康が入地して
関東全域の支配を固めるために都市経営をはじめた。
小田原という関東でもいちばん東海地域に近い軍事上の要害地では
全関東の中心地としては西に偏りすぎているし、
その後の「経済発展」のためには水運の豊かさが必須だった。
といった秀吉政権からのアドバイスがあったとされる。
俗に言う、小田原戦陣での秀吉と家康の逸話が有名ですね。
こういった中核都市建設については最新の事例は札幌。
日本史は奈良の都市造りから京都や大阪、江戸を経て
はるかに新開地北海道・札幌の創造へと至っているのだと思います。
いちばん新しい大都市開発で札幌には情報痕跡が多い。
日本社会はどう都市建設するか、その証拠が札幌には身近に存在する。
またそういう大都市造営の直近の先例・首都東京にはヒントが山ほどある。
そのなかでもとくに皇居の占める文化的位置関係が特徴的。
江戸・東京の場合、中心施設が明瞭。
現在の皇居、最初は徳川将軍の本拠地がすべての起点になる。
最初は大土木工事が行われ、巨大なお濠を持つ巨大城郭が誕生した。
その巨大なイレモノにまるで真空のようにいま、自然が回帰する。
いったんの大土木工事を経て成立した大都市の街区のなかに、
広大な緑の領域が広がっている。
世界の宮殿建築空間の中で、面積的には最大に近いのではないか。
自然崇拝型の最古級古代権力として存続している
日本の皇室という存在は世界で稀有な「文化資産」だと再確認できる。
土木工事の末の「回帰する自然」を日本は「崇拝」しているともいえる。
憲法第1条には天皇の条項があるけれど、
「統合の象徴」ということの意味合いは深まっていると思う。
世界標準からすればきわめて異様な存在ではあるけれど、
現代世界では特徴的な文化資産という側面が非常に強まってきている。
とくに分裂と対立が強調されるようなIT文明下では、
こうした「国民統合」神話を意図的に継続する国家意志というのは
現代で陳腐化するよりもむしろ価値を高めているといえる。
敗戦期にこの資産を守り抜こうとした先人たちの思いが伝わってくる。
世界の中で、この真空な文化資産がどう推移していくのか、
非常にユニークな試みをニッポンは行っているのだと思う。
Posted on 11月 18th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究 | No Comments »
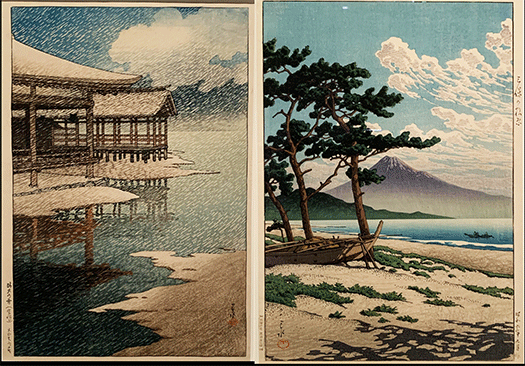
写真は竹橋の東京国立近代美術館展示の「河瀬巴水・東海道風景集」から、
三保の松原と厳島神社の版画です。
どうもわたしは日本の近現代の美術には関心が薄い。
油絵やモダンアート然とした作品群にはどうも拒否反応する。
っていうことをきのうも書いたのですが、展示にはそういうのが多くて
やや困惑していたところに、この画集展示があった。
この作品群は「東海道53次」的な下敷きで昭和7年に出版された作品。
いったいなにが描かれているか、素人的にはすぐ了解しにくい
難解なモダンアート作品群のなかにわかりやすい構図・絵柄が展開。
受け止め側では非常にわかりやすく感情移入しやすかった。
・・・で、ふと日本人はなぜ「三保の松原とか厳島神社」に代表される
「名所」という感覚を共有し続けてきたのかに思いが至った。
いうまでもなくこれらは「観光地」となっていまも惹き付け続けている。
この河瀬巴水さんもモダニズムという洗礼を受けた日本人で
そのうえでこういう「キッチュな」名所を再検索している。
油絵とか写真、モダンアートとかの「表現」が選択可能であるなかで、
むしろ伝統的な版画表現を使ってなお、名所を美的に再探究している。
たぶん作家の内面での興味は「なぜ日本人はこういうのが数寄なのか」
だったのではないかと伝わってくる。
三保の松原というのはどう日本人の「デザインコード」を刺激するのか。
平清盛の時代、厳島を造形した日本人の美の感覚とは?
そういうニッポン的なDNA感覚を突き詰める意志を感じた。
どうも、難解なモダンアートの薄っぺらさに比べて
こっちの方がはるかに根底的な探究のように思えてならない・・・。
昨日は「高輪ゲートウェイ駅」工事にぶつかって
東京都内で山手線内に入るのに大汗を掻いておりました。
土曜日なのに久しぶりに「ギュー詰め」電車移動を再体験。
夕方、札幌帰還したらこっちは静かな雪。
「ことしも冬か・・・」であります。
Posted on 11月 17th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究 | No Comments »
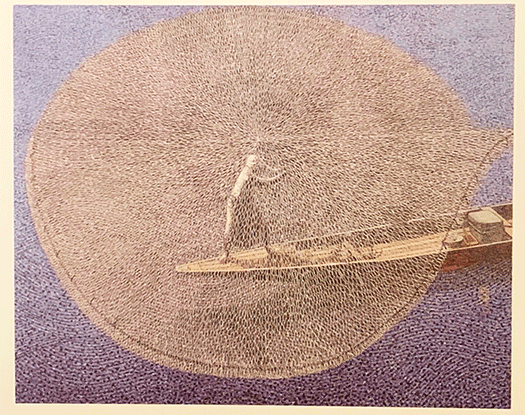
東京に来ると時間を見て山種美術館は必ず鑑賞する。
今回展示は「東山魁夷の青・奥田元宋の赤ー色で読み解く日本画ー」
いつのころからか、西洋絵画よりも日本画に強く惹かれるようになって
日本画の最大コレクション、山種美術館に吸引されている。
どうもこういった「伝統系」の方にどんどん惹かれていくのか、
建築でも伝統工法の技術伝承などにも親近感を持つようになる。
結局、日本という国は島国であり、海洋国家なのでしょう。
大陸国家というのはとにかく原理性に帰依してそれに非妥協的に固執する。
海洋国家はそういったものを柔軟に受け止めるけれど、
やがては咀嚼して独特に「国風化」させてしまう。
近現代で言えば、明治維新以降旺盛に西洋文明を受容してきて
世界がひとつの価値感に統合されてきたことの
ひとつのきっかけも作ったのだと思われる。
最近の歴史家のみなさんの話題展開を聞いていると、
西洋文明が汎世界性を持ったのには、日本の選択が大きかったと。
東アジアは西洋世界とはまた違った価値観である統合を見せていたけれど、
その因習の限界を真っ先に打破して西洋を受容した。
その結果、漢字やことばまで大きく改変して同化を進めた。
そのことで中国や朝鮮が西洋の作った「汎世界」に参加できる
地ならしもしたのだと思う。
しかし、日本は伝統的に旺盛に文化・文明を受容するけれど、
やがて「国風化」も揺り戻しで必ず起こってきた。
そんななかで日本画に惹かれてきている。
一部の「印象派」をのぞいた西洋絵画は言うに及ばず、
一部を除いた現代芸術などにはほぼ興味を持ちにくい。
その上、表現の不自由だなどと言うに及んでは単なるプロパガンダ。
そういう騒々しさは見たくない、もう勘弁して欲しい。
おっと、まったく論旨が外れてきた(笑)。
きのう鑑賞していて、この作品に驚かされた。
美術館のTwitterでは以下のような紹介。
「宮廻正明《水花火(螺)》(山種美術館)。画家自身によれば、
水衣という能装束に使われた絹を張り込み、
その上から細かい網目を描いた作品。水の表現には、
白群青(顔料)と藍色(染料)を幾重にも点で塗り重ねたそうですよ。」
とのことですが、
このテーマモチーフの漁業の一瞬を切り取る感性に
まったく圧倒されてしまった。
作家は東京藝術大学 大学院美術研究科 文化財保存学専攻教授とのこと。
これは「水花火」というタイトルをみれば「自然」描写でしょう。
目に見える対象に対して、それをどう受け止めるかは
人間それぞれでまったく違うということに強く気付かされる。
この作者はこの一瞬の刹那を切り取って絹のキャンパスに叩き付けた。
その叩き付け方がいかにも丹念な「日本」スタイル。
あくまでも細部、ディテールにこだわって細密に仕上げていく。
そういう結果としての仕上がりでは、
まず、その構図の斬新さに驚かされる。
四角いキャンパスに丸がくっきりと叩き付けられている。
背景画として人物と船の造形が夢幻的に描かれている。
「白群青(顔料)と藍色(染料)を幾重にも点」で描くことで、
画面全体に透明感ももたらせてくれている。
ときどき、こういうハッとさせられる絵と向き合うことがある。
ものすごくうれしくなる。
Posted on 11月 16th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究 | No Comments »

写真は先日下取材してきた北海道足寄町の木組みの家。
木組みの家は先日の「エコハウスコンテスト」by建築知識ビルダーズさんで
「漢方の本陣」というユニークなネーミングの家がリフォーム部門で
「大賞」を受賞されていました。
設計者の松井郁夫さんや断熱の管理の夏見さんなどが活躍された。
北海道の高断熱高気密派はこういった伝統工法の「対極」というように
見られる方がいるようですが、
むしろ工業化住宅、画一化住宅との関係で対極という意味合いで
共通する部分の方が大きいと思っています。
また、どちらも細部での施工が命という部分があって
親和性がむしろあるのではとないだろうかと。
伝統工法は写真のような「貫」とか「込み栓」のようなディテールから
非常にきめ細かな手順と段取りが要求される。
高断熱高気密でも、気密層の連続や断熱部位の処理方法など、
こちらも「施工」のきめ細かさがポイントといえる。
写真で見る貫などは、構造の柱梁の主体部分と同時に一気に組み上げる
必要があるので、工程管理では段取りが非常に重要になる。
それに気密層の連続、断熱欠損への配慮が加わることになる。
その両方をやらなきゃならないのは大変だ、という考えもありますが、
作り手のメンタルとしては共通性はあるだろうと思います。
こちらの現場では基本の木組みでは、プレカット工場などに発注し、
手刻みのような複雑な工程のショートカットにも努力したとされていた。
込み栓などの「調整装置」は、それを建て主が見続け、
維持管理の重要性を気にかけ続ける、という効果もあるだろうと思います。
こんな風に見えていれば、ちょっとさわってもみたくなる(笑)。
どうもこれからの住宅って2極化するのではないかと思います。
ひとつは合理化が究極的に進んで施工手間簡略化の方向になるもの。
こちらが一般的な志向になることはわかりやすい。
しかしこの方向では中小零細企業である地域工務店は
その「独自性」を発揮できるのか、不明なところがある。
合理性の土俵ではたぶん大企業型工場生産型に有利。
一方で手作りのぬくもりのようなものを求めるユーザーも残るだろう。
手作り、一品生産型の職人仕事が地域で希少価値を持つ可能性がある。
ただしユーザーは前者と後者の違いがよく見えないだろう。
そういったときに、いかにも手作り感が「見える化」した
こういった伝統工法+高断熱高気密が力を持つ可能性があるだろうと。
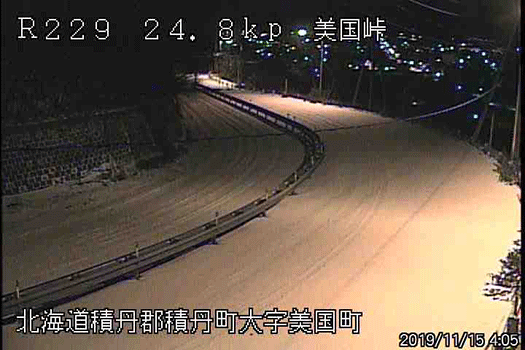
さてきのうから東京に来ておりますが、
留守を狙ってか、北海道は本格的に雪模様の天気に変わったとか。
汗ばむほどの11月中旬の東京。半袖の人も多い・・・。
Posted on 11月 15th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング | No Comments »
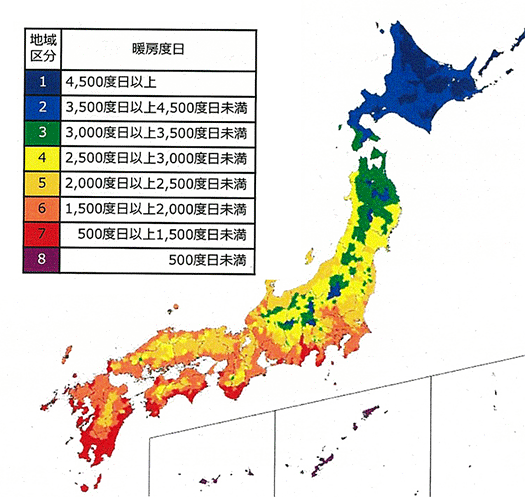
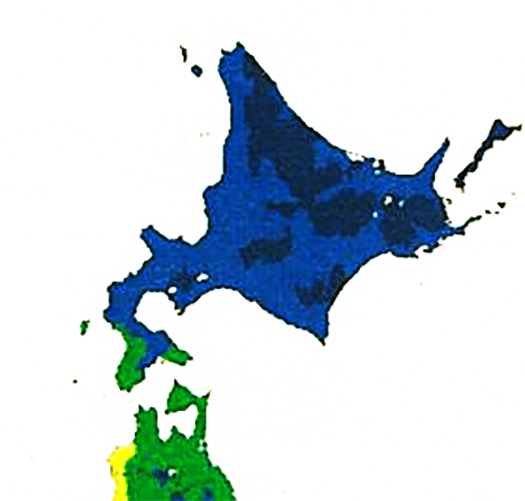
きのうは北海道庁の「北方型住宅」検討会議に出席。
この「諮問会議」座長はいま道総研理事の鈴木大隆さん。
会議ではこれまでの論議に踏まえて北海道としての
地域ブランド住宅として「北方型住宅2020」の創設が決まりました。
これはこれまでの「北方型住宅」「北方型eco」「北海道R住宅」などの
制度設計の流れを引き継ぐもので、住宅政策で日本全国をリードしてきた
北海道地域として、官民挙げて新時代の住宅施策を示すもの。
このあと年度中に再度整理整頓の会議が開かれて、
新年度から施策実施されていくカタチになります。
このブログでは「北海道住宅始原期への旅」をテーマ展開していますが、
地域としての北海道が歴史的に150年間取り組んできた
「よき住宅」のあり方について未来に向かってその方向性を
ふたたび明確に指し示すものといえるでしょう。
先人たちの住への思いを受け継ぎ、しっかり未来世代に手渡したい。
さて、そういう会議の中で鈴木大隆さんから「参考資料」として
表題とイラスト図のような資料が提示されていました。
これまでの「地域区分」を見直して今月から公布・施行されます。
この見直しと連動の「外皮基準の見直し」は2020.4月施行とされていました。
説明文は以下のようになっていました。
「最新の外気温データ(現行1981年〜1995年を1981年〜2010年に見直し)を
各地域の標高の影響を加味して補正した値に基づき、
地域区分の見直しを行う。その際、旧市町村区域に対して設定している現行
地域区分について、市町村の意見を踏まえた上で、現状の
市町村区域単位で地域区分を設定する。」とのこと。
これまでの1981年からの15年間データから30年間データに改める。
その結果「暖房度日」〜基準温度14度以下の日数〜が
図、左側の表のように整理されて、右側の日本の各市町村ごとに
置き換えて表現すると色づけされた地図のようになる。
その変化・推移をたとえば下の図の北海道単体で見てみると、
旧来の1−3地域という区分自体は変わらないけれど、
これまで7割程度が1地域だったものが、3割程度に変わった。
気候変動による「温暖化」が浮かび上がってくる。
しかしそうであっても、多数派になった2地域でも暖房は年間で
116日から150日程度必要な厳しい寒冷地であることは間違いがない。
さらにこうした温暖化は、また別の気候変動危機をもたらせている。
直近のオリンピックマラソンの会場変更もあったように、
温暖地域の蒸暑が危険な領域まで進行してきたことや、
その上気候変動が大規模災害、台風の巨大化などを引き起こしてきている。
対抗するための最大要素技術が「断熱気密」であることはもちろんですが、
その効果を最大化させる努力は待った無しで求められています。
安全安心の家づくりの探究はまさに、正念場といえるでしょう。
Posted on 11月 14th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング | No Comments »
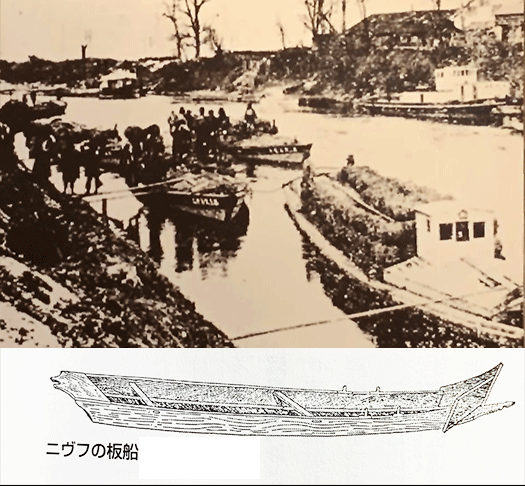
本日から住宅ネタに復帰としましたが、
書き進めていて気付いていたことがあるので、書き留めておきたい。
というのは、昨日まで数回にわたって書いた「阿部比羅夫」の
北方遠征に関連してのことです。
この遠征ではヤマト王権側の狙いは安定的な北方交易の確保だっただろうと
思います。日本書紀にわざわざ「生きたクマ2匹と毛皮70枚」と
その「交易品」が記されているのは、
こうした交易品が王権社会で珍重され「威信材」として
各地のヤマト政権への服従を誓う豪族に対して「下賜」される
その対象だったのではないかと推測されるのです。
この時代以降、奈良期の黄金発掘などもあって北方への関心が
非常に強くなるのは、こうした交易の魅力が深く浸透した証しだと思える。
一方で、阿部比羅夫は北海道現地の2つの勢力のうち、
続縄文の社会側と同盟関係になったことが見て取れる。
戦争後、王権の地方統括システムとしての「郡領」を「任命」した
事実もあるし、1000人もの「軍勢」が奥尻島攻撃に対して
後方兵站を担ったとされたりもすることから自然な理解でしょう。
既存の石狩低地帯以西の続縄文社会は、北東アジアからオホーツク海岸に
勢力拡大してきた「粛慎」オホーツク文化社会の脅威にさらされていた。
その脅威表現で「北方から大船で押し寄せる」と日本書紀に記述。
ということは、社会として大型海生動物・鯨などのハンティングに
高い能力を持っていたとされるオホーツク文化の人々は、
そうした優越的軍事行動力として、生業との関連で
「大型舟運」に先進的能力を持っていたことが推定される。
石狩低地帯以西の続縄文社会が持つ伝統的な舟運手段は
丸木舟程度だったので、彼我の機動力に大きな格差があった。
この軍事力の格差について、阿部比羅夫の日本王権社会に助けを求めた、
という流れがいちばんスッキリと腑に落ちるのだと思う。
瀬川拓郎さんの著述での解析で奥尻島で戦闘が行われ、
島に立てこもったオホーツク文化の人々を攻撃し陥落させた主戦力は、
王権側の「水軍力」だったのだろうと思われるのです。
ただし、兵力自体は王権社会の構成員だけではなく、
東北北部の「蝦夷」の人たちが担っていたとされる記述も見られる。
写真は明治初期の石狩川周辺での舟運の様子です。
オホーツク文化と近縁と思われる北東アジアの民族「ニヴフ」社会の
当時としては大型機動力としての前述の「大船」イラストと酷似する。
どうもこれが660年頃の阿部比羅夫遠征のキーポイントと思われてなりません。
Posted on 11月 13th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 歴史探訪 | No Comments »