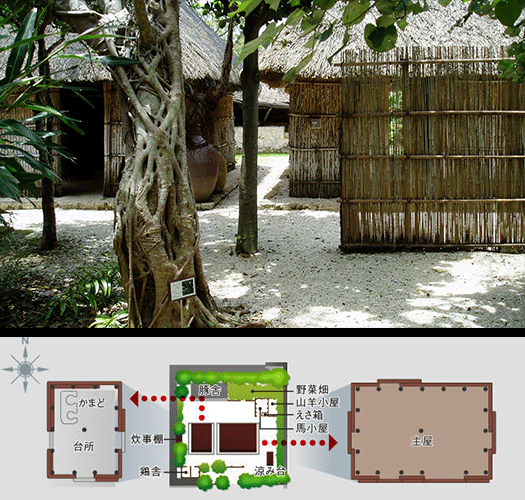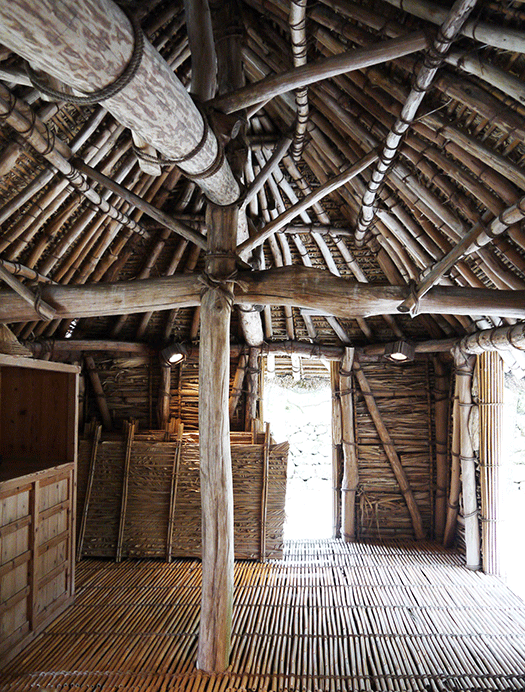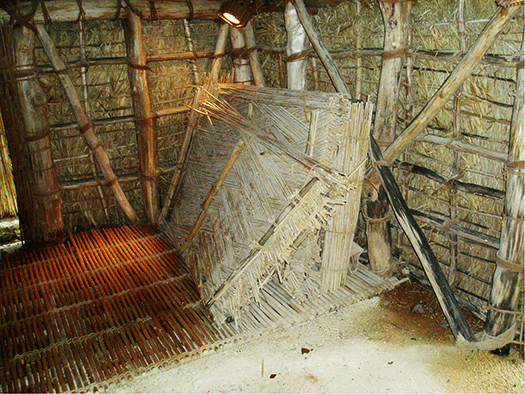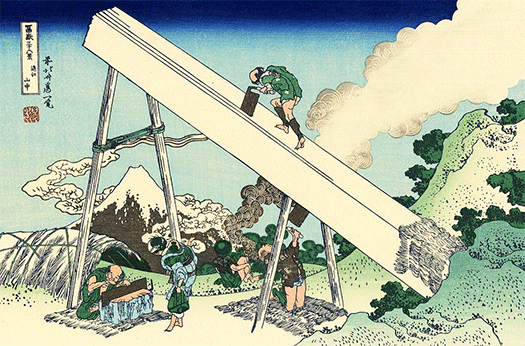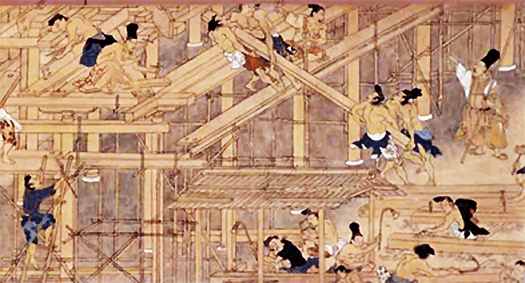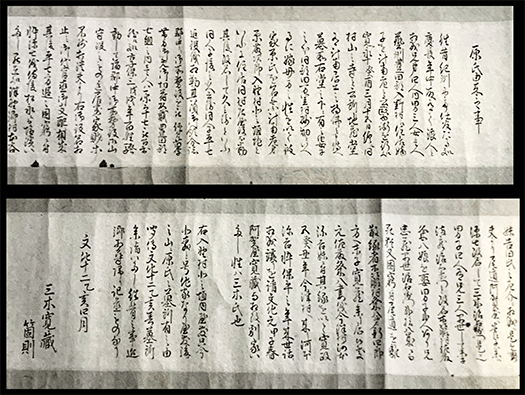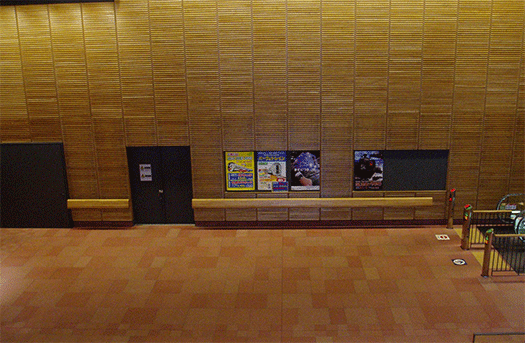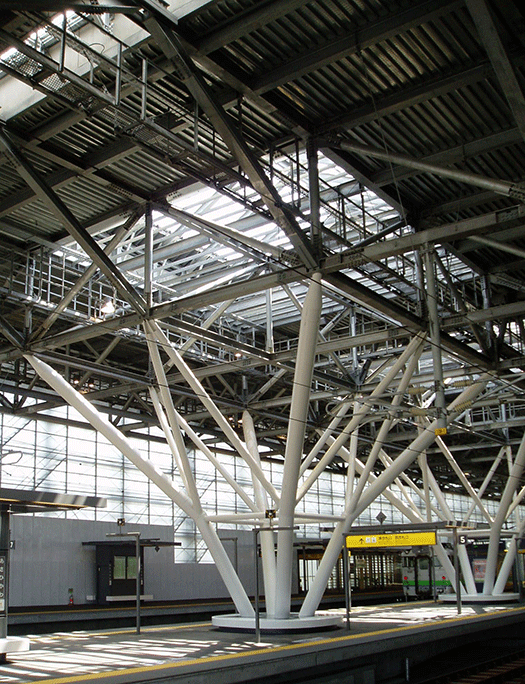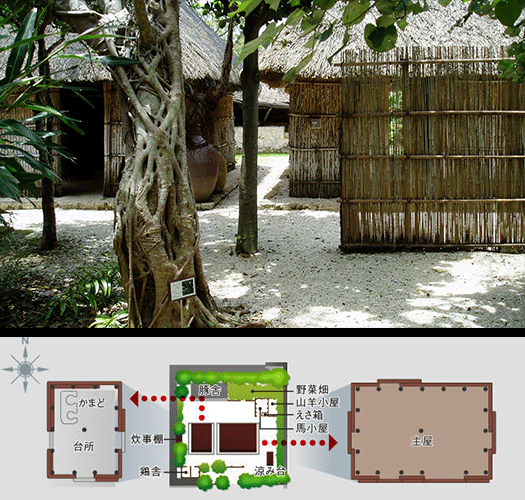
北海道で住宅の情報を扱う仕事をしていると
逆に南方での家の成り立ちとか、発展形態とかに興味を持ちます。
いろいろな機縁が重なって、沖縄にはたびたび訪問「取材」してきた。
古民家として、中村家住宅などは5-6回見学している。
写真の「おきなわ郷土村」の古民家群も数回見学して来ています。
もちろん現代住宅も見学していますが、
現代住宅は衣食住すべてにおいてグローバル化が進んでいて
地域オリジナルの基底的「文化様式」とは変容している部分がある。
やはり地域固有のありようは、古民家から浮き彫りになってくる。
少なくとも、そこで暮らす人間のライフスタイルとしての重要な要素が見られる。
そういうものが知らず知らずに、現代住宅にも「色づく」ものでしょう。
この家は年代特定はなかったのですが、
与那国島で「かつて建てられていた」住宅の移築という説明。
写真下に「間取り図」も付けましたが、2棟の建物で居住空間が構成されている。
いわゆる「分棟」形式ですね。
現代の北国住宅では基本的に「外皮表面積」を最小化方向で考える。
それは、熱損失を最小化させるという合理性志向からの選択。
暖房が基本になるけれど、家の中の温度をコントロールするためには、
必然的になるべくシンプルボックスである方が合理的。
家の機能も、当然、あるボックスのなかに詰め込む方向で考える。
わざわざ機能ごとに棟を分けるという発想を持たない。
伝統的には馬小屋までも一体空間で取り込む「南部曲がり家」的方向。
しかし、人類の住宅の中には南方系で「分棟」という形式もまた多い。
この与那国の家では、植栽樹木や「ヒンプン」という
ウチソト仕切り装置内部のなかに「イエ」という結界領域があって、
「屋敷には主屋(ダ)、炊事場(チムヤー)のほか、周りに家畜小屋、
小さな野菜畑が配置されて一般的な与那国の農家」が構成されている。
大阪住吉では現代コンクリート住宅で安藤忠雄さんが家の中で
傘を差して室内移動する住宅を建てたことが、センセーションを呼んだワケですが、
ここでは食事をするたびに外部を通ることになる。
まぁ、ほとんど距離はないのだけれど、空気環境は外部と一体型。
平均気温では冬場1月でも18度前後、最低でも16度程度なので、
着衣程度で過ごせることが大きく、むしろ煮炊きする熱気と湿気を
通常生活とは完全に切り離す方が合理的であるという「暮らしの知恵」。
また一般的に敷地が90坪程度あり、菜園なども含めた空間が
「屋根はないけどイエ」という意識になっているのだと知れます。
だから、ヒンプンという住の装置が結界装置として機能するのでしょう。
寒冷地でもたしかに「敷地」概念はあるけれど、
ヒンプンというようなものが結界を構成するという考えは少ない。
それよりは、より重厚に「壁を作る」方向に向かう。
でも寒冷地人間にすると、こういうあいまいな住空間意識というものに
強く憧れを持つ部分がある(笑)。
こういう「融通無碍」な建築が、どういうライフスタイル精神を生むか
その、得も言われぬ「開放感」に強く惹かれるのです。
意思疎通が普通にできる言語文化を共有しているのに、
ここまで「イエ」概念に違いがあることに強く刺激されます。
Posted on 8月 25th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究 | No Comments »
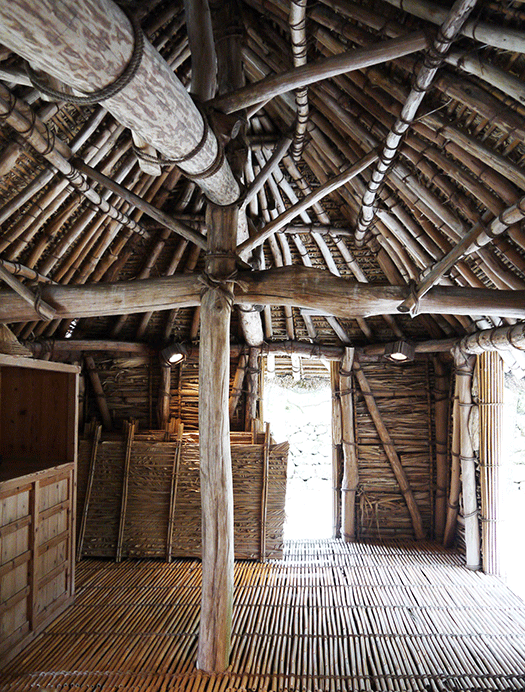
きのうは「たたみ」の発展過程の探究を考えましたが、
写真は同じ、おきなわ郷土村に建てられている復元古民家・与那国の家。
で、本日はほとんど製材していない柱と梁を縄、もしくは
つる性植物で結束させている「架構」を見たいと。
先日も、三内丸山の縄文復元建築と吉野ヶ里の弥生復元建築の
「木組み構法」の違いを見たのですが、
あれは年代的にはそれぞれ、5,000年前とか1,800年前とかの想定。
それに対してこちらの建物は、基本的には移築復元とされているので、
ごく近年まで実際に建っていた住宅ということ。
どんなに古く考えても、100-200年程度の過去ということになる。
であるのに、木組みの構法として結束がつる性植物。
しかも構造の建材・木も未製材の自然木が使われていました。
壁や床、屋根の骨格についても、竹を組み上げて造作していた。
製材した材料ではないので、直線的な均整感よりも、
それこそ竪穴住居的なバイタルな印象に近い建てられよう。
自然派志向的には究極的なエコロジーを感じる(笑)。
しかし、きっと建てた人たちには止むにやまれぬ選択だったのでしょう。
こういった「民家」は、構造部分だけは大工職人が基本を作って
そのあとは建て主・住まい手が材料集めも含めて
DIYとして「施工」まで行ったのが普遍的なありようだったのでしょう。
もちろん近代国家が「建築基準法」的に制約を加えたものでもなかった。
しかしその「依頼」には当然「手間賃」費用負担は当然あっただろう。
また、与那国島にそういった大工職人が定住していたとも考えにくい。
そこに住むことを人生選択した人間が自分自身のため、家族のため、
手作りで挑戦していたに違いない。
そういうことで考えれば、主体構造である柱と梁を結合させるのに
複雑な工具・建築知識を必要としない建て方として、
こういった「構造」は、自然発生的でわかりやすかったでしょうね。
たぶん材料の類は、その建物周辺から自分ですべて探し出してきたのでは。
アイヌのチセの場合も、家を新築するのは結婚の時点が多く、
材料は新郎が自分で集めてくるというのが「しきたり」だったとされる。
定かではないのですが、想像としてはそのように考えられる。
その時点で建てられていた家の構造を見て、
それを「モデル」として「見よう見まね」で建てたというのが自然。
施工についても、近縁者が労働奉仕していっしょに作ってくれた(笑)。
きっと新婦はそういう助けに来てくれた人に手作りの食事を作って
感謝の気持ちを表した、っていうような風景が思い浮かびます。
現代のように、ひたすらお金に換算した建築のありようと、
どっちが家づくりで「楽しいか」は、なんとも言えないでしょうね(笑)。
Posted on 8月 24th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究 | No Comments »
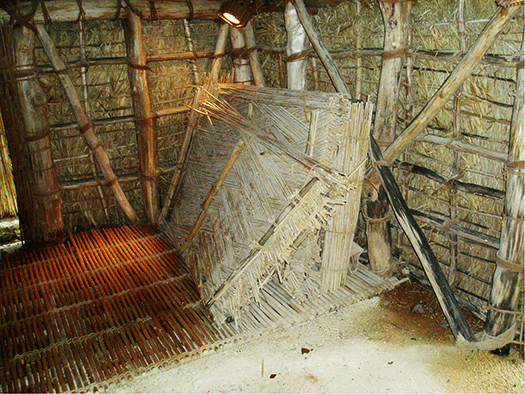

見学していたそのときに、ふと気付いていたことってたくさんある。
そういうことはしかし、通常の仕事の流れの中で、あるいは
スケジュール的な時間進行に埋もれてしまって、その場だけの
気付きに留まってしまうことが多い。
取材写真の再整理によって、そうした「点」が「線」になることがある。
提示した写真は、上の写真が2006年沖縄の「おきなわ郷土村」で見学した
「王国時代の民家」の室内の一隅に置かれていた「敷物」。
琉球王国時代(1737~1889年の間)の住宅ということなので約200年前ころ。
下の写真は、2005年に見学した吉野ヶ里の「権力層の人間の家」寝室。
吉野ヶ里は、だいたい3世紀(200~300年)頃を復元想定しているよう。
その両方で見た、畳の祖形とおぼしき敷物であります。
どうもその「類似性」に気付かされていた次第なのです。
しかし、時代としては1500-1600年くらいの間隔がある。
九州と沖縄、社会発展には多少の差異はあったとはいえ、
この時代、琉球は薩摩藩の実質支配という歴史時間に相当する。
自然にある植物繊維質を「編み上げて」敷物として利用する、という発想は
人類に広く存在しているけれど、
日本でだけ、畳という敷物が発達して主流になった。
その祖形がムシロのようなものから発展したことは、自然でしょう。
この写真の両方から、ムシロをさらに重層化させている様子がみえる。
琉球王国の時代というのは、江戸期の身分制規範が連動した時代で、
庶民の住宅にはいろいろな「建築制限」が設けられていたという。
〜身分によって屋敷や家屋の大きさが制限され、
農村では屋敷(敷地)が9間角(81坪、265平方m)、
家屋は4間に3間の主屋一棟と、3間に2間の台所一棟に限られました。〜
この時代、当然「畳」というものは開発され流通もできたであろうことは
明白ですから、この「制限」によって畳が禁制されて、
その法令逃れのため「いや、これはムシロですよ」という便法をとったのか?
よく見てみると、骨組みも木材や竹で組まれているようで、
その表皮としてムシロ状の素材によって被覆構成されている。
吉野ヶ里の場合には床は土間が想定されていて
その土間に段差を付けて一段高くした箇所を「寝室」としている。
その土間上に、こうした寝具敷物が敷かれていた。
一方の沖縄では、この家の床は竹で仕上げられています。
壁も植物繊維を組み上げて壁面を造作していると同時に
床面も土間から少し上がっていて空気流動が仕掛けられている。
蒸暑気候に対しての室内環境制御として、なんとなく「うっとり」するいごこち。
そこでの寝具・敷物として、こういう装置があったようです。
やっぱり、土間や竹の床だけよりも、こういう繊維素材の方が
カラダにとって、就寝時には好適な環境を作ったのに違いありません。
どちらでも「掛布団」状のものがありませんでしたが、
まぁ一般的に考えて、ムシロ技術で応用造作されたのでしょうね。
どちらも復元住宅ではありますが、
それぞれの地域の気候風土を考え合わせると、
人間居住環境への最大限の努力追求の痕跡があきらかだと思えます。
Posted on 8月 23rd, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »
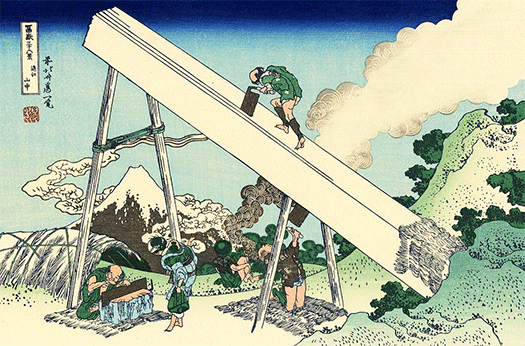
ブログ執筆を通して自分の興味分野を再度、探訪しています。
デジタルデータに残っている取材「写真類」は膨大で
とりあえずはその写真データの点検、チェックから徐々に進めている。
おおまかに時間経過、探訪年順に整理整頓しようとしていますが、
少なくとも18年分くらいあるので、
まことに膨大なチェックが必要です。たぶん写真店数は数万点超・・・、
データの総量は、273.78 GB、49,997項目にもなっている。オイオイ。
お盆休みを利用して集中的に時間を掛けたのですが、
なんとその作業をしていると、パソコンに向かい続けるので
背中中央部に激痛が発生してしまった(泣)。
どうも猫背っぽく姿勢が固定されるので、カラダからの悲鳴でしょう。
人間は住宅というものをどう作ってきたのか、
その興味に即していろいろな取材をしてきていることが再確認できる。
いろいろな学究のみなさんの知見にも導かれながら、
具体的な「見える化」可能な表現を考え、手掘りしていく作業。
建築ジャーナリズムというようなものが、
わたしが選択した領域なのだと考えると、
きのうも書いたような建築工事現場の古絵画記録などに
非常に近縁感を持ってしまいます。
きのうはどちらも鎌倉期の春日権現験記と松崎天神縁起を見た。
春日大社には2度ほど見学に訪れている、その体験記憶も重ね、
建築取材というようなバーチャル「体験」を構築してみる。
あるいは青森の三内丸山にはそれこそ4−5回行っていますので
そういう具体的な空間記憶蓄積が濃厚にある。
空間の把握体験があることで、徐々に思惟が膨らんでいく。
木を加工するということの推移、経過、歴史のようなこと、
そうしたことが、非常に興味深くなってきています。
写真絵画は、江戸時代後期の「木挽」たちの仕事姿で、
葛飾北斎『富嶽三十六景』の「遠江山中」1830年ころ。
この絵は大鋸で太い原木から幾枚かの「板」を製材・木挽きしている。
材の上に乗って木挽きする人と、下から見上げながらの2人組。
この材をどうやって立てかけたかも興味津々だけれど、
板に製材加工する大変さに北斎も驚いていることが伝わってくる。
きっとコストも考えた職人としての技量向上から
なるべく用を足せるギリギリの薄さ、軽さを追求したように思える。
木の属性・性質を知って良さを際だたせることも考えただろう・・・
たしか、千葉県の歴史民俗博物館での展示でもこの大鋸による木挽きの
様子が大きくジオラマ展示されていました。
歴史発展は、技術の進化と拡散が同時進行したのでしょうから、
表面の政治史の裏側で、こうした技術革新が基盤を作ったという表現。
鎌倉期の図を見ていて、製材作業の様子にも気付いた次第。
「板」というものの製造の歴史というものに興味が深くなる。
鋸や工具がどのように進化して、工事現場がいかに変化してきたのか、
その結果から、工事のコストを推定して、
その歴史社会のなかで当該建築が占めていた重要度なども
大きく想像することが可能だろうと思います。
たぶんそれぞれの歴史年代の人々は、そうした建築に「驚かされた」。
そのオドロキをしっかりとジャーナリズム的に再構築したくなるのです。
Posted on 8月 22nd, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »
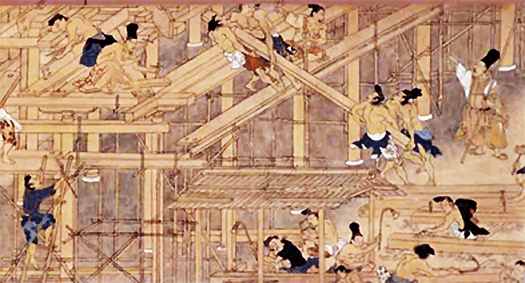

大好きできわめて貴重な民族資産だと思っているものに
「春日権現験記」があります。
(写真順番を間違えました。春日〜写真は下。上は同時代1311年頃に
描かれた松崎天神縁起〜こっちも職人さんの体技描写がすごい)
1309年(延慶2年)に時の左大臣・西園寺公衡の発案で、
宮廷絵所の長・高階隆兼によって描かれ、春日大社に奉納された。
<最高峰の大和絵で描かれた社寺縁起絵巻の代表作であると同時に、
全巻が揃い、制作者が判明していることや、
当時の風俗が細かく描かれていることなどから、日本の中世を知る
貴重な歴史的資料とみなされている>というものです。その目的は、
<藤原氏一門の繁栄を祈願するために春日明神から受けた加護と霊験を綴った
絵巻物であり、詞書の執筆は鷹司基忠とその息子・冬平、良信(興福寺学僧)
冬基の3兄弟が担当し、編集は興福寺の学僧・覚円(西園寺公衡の弟)>
絹本著色、巻子装、全20巻(他に目録1巻)、三の丸尚蔵館所蔵。
春日大社なので、藤原氏一族の繁栄ぶりを誇るものとして
その当時の最高技術を結集した建築の詳細工事の模様を
かなり克明に「メディア化」した一級資料になっている。
700年前当時の大工職人さんを中心にした人間の生々しい表情が活写される。
絹本という、絹地に着色するという形式で描かれている。
そもそも絹地であり、それ自体が相当に高価なもの。
<絵画史上きわめて貴重な作品であるとして2004年から15か年計画で、
原本の全面的な解体修理と調査が行なわれている。
表紙裂の復元には、一般種の繭から作った絹糸では太すぎて風合いが
出せないため、天皇家が育てている古代種繭の「小石丸」を使用。>
と記述されているように、民族の宝物として現代技術の粋を傾けている。
わたしどもは住宅雑誌・WEBメディアを業としているワケですが
とくに鎌倉期の建築が表現されている絵画部分について
そのはるかな先達として、仰ぎ見るような思いを抱く次第です。
大工仕事というのは体技技能としてカラダで伝承させるものであり、
絵画として具体的なイメージをもって「伝えられる」のはまことに稀有。
これらに描かれている大工や職人さんたちの体技、表情などから
まことにたくさんの「情報」を受け取ることができます。
デジタル時代になって、こうした情報資産が容易に共有されることは、
本当に素晴らしいことだと思われます。
この700年前の表現者のみなさんは、主に「大和絵」という
ツールを使って現代にまで貴重な情報をくださっているのですが、
現代では基本的には「写真」という媒介をつかって
わたしたちは日々、建築を「伝えよう」としている。
この表現を見ていると藤原氏の氏神礼賛や縁起説明という目的を
遙かに超越して、時代の空気感が直にカラダに伝わってくる。
先人たちの息づかいに深く目を凝らされております(笑)。
Posted on 8月 21st, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 歴史探訪 | No Comments »
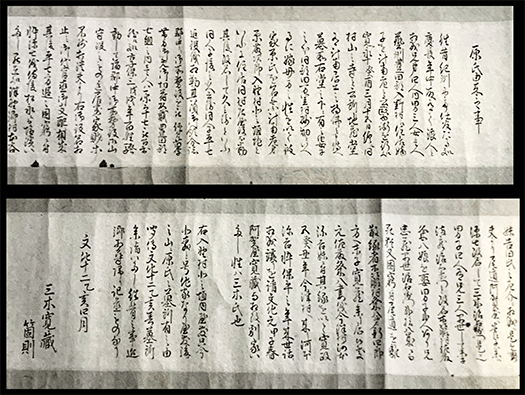

本日はわたしの「歴史好き」の機縁になっている家系伝承テーマ。
本来の住宅ネタはお休み。あしからずお許しください。
写真はわたしの家系に伝わっている希少な「書き物」。
文化12年乙亥4月という日付が記載されているので、
1815年4月というように特定できる。今から204年前。
世情は幕末で、活発に外国船が日本に来るようになっている時期で、
北前船交易で高田屋嘉兵衛さんが活躍した時代。
わたしのご先祖さまは尾道周辺で商家として活動していた。
で、わたしはいまは「三木」姓ですが、
江戸期までの日本社会は「家」は必ずしも血縁関係がすべてではない。
むしろ家の存続のために活発に「養子」とか「縁組み」がされていた。
なんと、1742年頃に原氏から「三木氏」に縁組みされているようです。
そういった経緯から、著述者である「三木寛蔵」さんが、
その血族として本来の縁である「原氏」の故地を探訪するために
下の写真のような位置関係で旅をして、そのときに見聞した記録を
後のわたしたちのために書き置きしてくれた書状なのです。
距離的には45km前後なので、往復と調査でたぶん4-5日程度の旅程でしょうか。
ちなみに書き手の寛蔵さんは年齢45歳なので歩いて1日の距離。
その記録で期日は明瞭ではないけれど、「慶長年中」に
「故あって」この探訪目的地・広島市河内町入野に入植したという記述。
慶長という年代はちょうど関ヶ原合戦が慶長5年(1600年)にあたる。
江戸時代というのは徳川の武家政権の時代であって、
こういう「お上」の支配する時代にあって「故あって」と書くのは
ふつうに考えれば、書き記すのに「憚って」ということと想像できる。
「往昔、紀州にて仕官たるところ」と書かれている。
この当時の紀州は豊臣秀長領で、代官桑山氏が実質領主の時代。
一応は縁も強いから表面的には西軍側だろうけれど、
主人・秀長亡き後、城代としては特段そのような思い入れはなかっただろう。
関ヶ原では桑山氏は東西両端を持していたことが容易に想像できる。
たぶん政治工作がうまくいって東軍側とされて生き残っている。
しかしわがご先祖はたぶん西軍側に「派遣され」その後、
勝った東軍側に転換した主家の方針から
自動的に「切り捨てられた」というような経緯が想像できる。
このような複雑な「経緯」すべてふくめて「故あって」と記載したのでは。
その後、入植した入野でそれほどの時間経過もなく「庄屋」になっている。
桑山さんから「退職・手切れ金」がそこそこ得られた可能性がある・・・。
っていうような、妄想をかき立てられる書状(笑)。
しかし妄想ではあっても、子孫としては有為転変の状況に
先祖がどのように対応してきたか、大いに想像力を刺激されている次第です。
Posted on 8月 20th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »

表題のようなことが、いま大きなテーマになって来ていると思います。
WEBの生成・発展のプロセスはそれこそリアルタイムで
わたしのビジネス環境として経験してきたことです。
業務にパソコンが導入されて、そのように仕事環境が再構築されていった、
そういった「導入期」を経て、その後はWEBという情報流通手段が発達した。
そういう環境にいち早く対応したいということで、
わたしは、既存の新聞やテレビという情報摂取スタイルから
WEBでの情報接触を中心にして、体感的に対応しようと考えた。
早々に新聞の購読をやめたり、テレビについてはもっと前から
そういう情報接触手段としては時間を大きく減らしてきた。
たぶんそういう「情報環境」になってからでも20年近くなっている。
こういう環境になってみていちばん気付くのは、
少なくとも日々の情報の中で大きな領域である政治・時事については、
WEB環境によって大きく社会が変動してきたということ。
つい先日もアメリカのトランプ大統領が韓国訪問に際して
北朝鮮の金正恩にTwitterだけの情報発信で「呼びかけて」
「近くまで来たから、顔を見せろや」的なノリで急遽、板門店で会談した。
国際政治情報でもWEBによる情報対応が、既存のメディア濾過されたものより
はるかに直接的に現実を動かし影響することを露わにしたと思う。
国際政治的にはトランプには「現状維持」が作戦であり、
金正恩個人の内面に「くさび」を打ち込んで、暴発させずに
確実な経済制裁によって北朝鮮が変化せざるを得ない状況に追い込んでいる。
そういった「対話」戦略に、Twitterが効果的に機能したのだろう。
こういった情報戦の「変化」に対して政治時事を主要な興味分野としている
既存の新聞メディアは対応できず影響を及ぼすこともできなかった。
既存の「思潮訴求型」メディアでは現実を捕捉できないことが浮き彫りになった。
WEBでは、まずはポータル・yahooなどの「トップページ」で
全体でのクリック数の多寡などによって「選別された」情報が提供される。
「いかに端的に伝えるか」に特化した「見出し」から情報接触が始まる。
<これは興味深い日本語の変化をもたらしてもいる>
このとき、ふつう情報提供先が朝日新聞か産経新聞かは、ほぼ顧慮されない。
そこから自分の「知りたい」内容に適合した「WEB情報取得」が始まる。
そういう個人の「情報接触傾向」はデータとして処理されて
「あなたへのオススメ」という情報項目がその下段に情報提供されている。
よく、WEB時代になって「社会の分断」が進行していると言われる実質は
こういったAI的な情報選択過程が反映されたその社会的表現なのだと思う。
ただ、こういった各自の「情報メディア」企業にとって、
主要な経済的構造は既存の紙メディア「販売」とその広告価値でしょう。
そのための広い意味での「広報拡散」としてWEB利用があるのだけれど、
どうしてもそこからの収益という構造がみえないままで来ている。
WEB課金というところでほぼ直帰するケースが多いのが現実。
全世界でメディア企業が直面している最大のネックなのだろうと思う。
しかし、ではこういう情報提供メディアがなくなった場合、
WEBの情報世界は大きく毀損するだろうことも見えてくる。
情報を掘り起こし、その意味を多くのひとに「伝える」仕事には
それを可能にするための「コスト」が絶対的にかかるのだ。
現状の情報提供環境では、このコスト循環構造が達成されていない。
21世紀はじめという現代での大きな問題としてこのことはあると思う。
巨大化した恐竜が地球環境変化に対応できず絶滅し、より小型の恒温動物である
哺乳類が地上を制覇したようにメディアも変化から逃れられないのでしょう。
Posted on 8月 19th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: Mac.PC&DTP, 住宅マーケティング | No Comments »
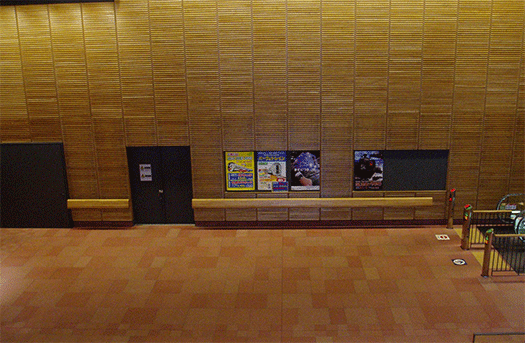

写真は2011年、オープンしたての頃に撮影していたJR旭川駅舎の内部。
平成29年度の統計では1日乗降客数が10,558人とのこと。
ちなみに北海道内のベスト15駅は以下で、旭川は全体の15位。
順位駅名乗降客数(人/日)
1位札幌19万5304人
2位新千歳空港3万2242人
3位手稲3万1178人
4位新札幌2万8534人
5位琴似2万3354人
6位桑園2万0590人
7位小樽1万8112人
8位千歳1万7498人
9位白石1万6154人
10位北広島1万5154人
11位大麻1万4470人
12位恵庭1万4460人
13位野幌1万3256人
14位星置1万2552人
15位旭川1万0558人
<「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省国土政策局・平成29年度)>
単純に乗降客数だけが交通路線の重要度を表すものではないけれど、
経営として考えれば、そういう要素でしか収入サイズを想定できない。
人口規模の大きな地域ではその内部で相互に移動することが多くなる。
それに対して、地方では「わざわざ」しか移動しない。
まぁ通常はほとんどクルマでの移動が主体になってしまうのは仕方がない。
たぶん、駅舎の大きさとしては札幌とも遜色がないほどですが、
人の移動のための施設・駅舎内を撮影しているのに人が映り込まないことが可能。
首都圏で言えばボリューム的にはターミナル駅に相当するのに
乗降客数では前橋(10,682人)くらいに相当するようです。
しかし、日本最北の基幹的交通ネットワーク拠点という意味合いは大きい。
ちなみに新幹線のある秋田とか、山形もちょっと多いくらいなので、
人口条件的には、健闘している感じでしょうか。
将来的には新幹線の開通も視野に入れて構想された駅舎。
そういうことなので、駅のデザインという面では素晴らしい。
積雪荷重を支え巨大な「開口」を持ちながら、なお「暖かく迎える」
といったデザイン意図を強く感じさせてくれている。
鉄骨フレームの幾何形状が巨大な屋根を支えているプラットホームは
一昨日写真でご紹介しましたが、本日は動線各所で
「木の街」旭川にふさわしい木質デザインの駅舎内部の様子。
1枚目の写真は1階の改札から上のプラットホームに上がるための
広いエントランス空間ですが、壁面一杯にタモの木が貼られている。
こんな指標があるかどうか知りませんが、
一人あたりの内装「感受」面積は、まことに広大ですね(笑)。まさに目に贅沢。
毎日、巨大利用者数の駅でゴミゴミ感を味わっているみなさんには
たまにこういう広大無辺感をぜひ味わっていただければと思っております。
まさに「でっかいどう・北海道」そのものかと。
Posted on 8月 18th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 「都市の快適」研究, 住宅マーケティング | No Comments »


きのうの続篇ブログであります。
この写真の「英賀神社」については、数回取り上げてきています。
播州のこの「英賀」は、夢前川河口に位置していて
地域一帯がわたしの家系の伝承に連なっていると考えています。
ときどき出張や旅行で訪れる機会があり、
そのたびにこの「拝殿」をたのしく見学させていただいています。
いまは、たぶん建築基準法上からの判断で不適と見なされ、
建て替え工事が行われ、先日「建前」が行われたと地元の議員さんの
ブログで紹介されておりました。
秋の例大祭でのお披露目を目指して急ピッチで工事進捗しているようです。
北海道人というのは、こういった「産土神」というような生活文化を
ほとんど感じないで育ってきている。
神さまというのが、もともとその地を開拓した伝承に基づいている産土信仰、
そういった感覚からはまったくほど遠い。
神社もそれこそ官製の「北海道神宮」など、戦前に国家が建立した
そういった存在しか、北海道人としては馴染みがない。
そういう理解に対して、この英賀に来てはじめて「産土」ということを
はじめて知らされる思いが強いのです。
とくにこの「拝殿」建築は、内部に入ると絵馬堂という機能も持っている。
絵馬というのは、北海道ではいきなり近現代の小さな絵馬しか想像しない。
地域社会から寸志が寄せられていわば「公共」として
大きい絵馬を奉納するというようなことがこの英賀では連綿と行われている。
日本の歴史とともに長くそういう民衆的な価値感が継続してきている。
一方北海道では地域社会が歴史が浅いためにいきなり現代的な契約概念的で
いわば地生えの「パブリック」というものが存在しない。
官製の神社としてしか存在しないように思うのです。
そういう近現代の「常識」的価値感からすると、
自然発生的なパブリックの意思が歴史的に継続しているというのは、
大いに驚かされ、また深くリスペクトを感じさせられる。
掲額されている絵馬群のいかにも大衆的な絵柄、わかりやすさにも
「ニッポン的地生え民主主義」みたいなものを感じさせられる。
たしかに戦前の一時期、国家神道のようなカタチで産土神も編入されて
変容させられた一時期はあったのだけれど、
それをただただ全否定していては、ニッポンの民衆の歩みも見えなくなる。
こういった神社仏閣がニッポン的「公共」社会のきわめて重要な
ファクターでもあったのだということが見えてくる。
単純に「政教分離という一神教」理解では、歴史も見失うと思えます。
Posted on 8月 17th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »

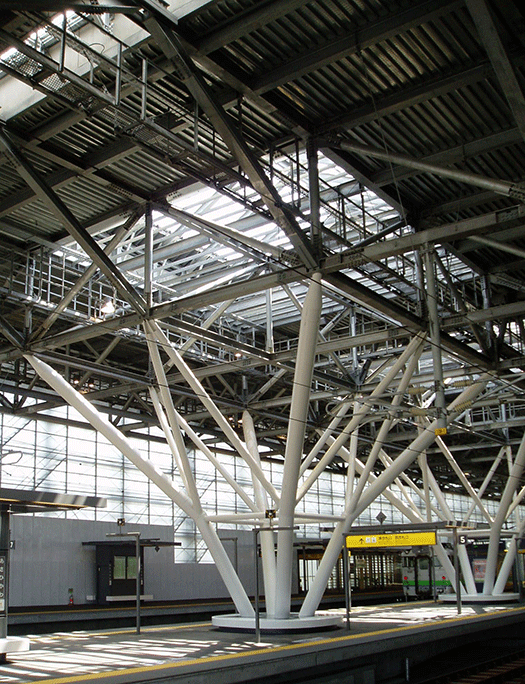
きのうも1日、義母の遺品の整理整頓作業をやっておりました。
っていうか、こういう作業は男はほとんど役に立たず、
ひたすらカミさんと娘の女子軍団。
で、わたしは付き添い&食事作り役に専念しておりました。
で、その間、前からやらなければと考えて休み期間中継続している
大量の「取材写真」類の大整理を継続しておりました。
デジカメやiPhoneのカメラ機能に写真撮影ということが移行して
それからでももう20年近く経っていますが、
だいたい年に20〜30箇所以上で自分自身の「強い興味」のままに
写真を撮り続けてきています。
ありがたいことに、そういう写真類がパソコンというツールで
保存され続けているワケですね。
写真類を一部は修正などもかけて整理整頓しているのです。
そういった記録が可能になってきて、それで気付くことというのがある。
そうです、自分自身の興味というものが明瞭に浮かび上がってくる。
やはり建築というもの、古今の建物についてっていうか、
その中でもある特定の領域について強い興味のありかが見える。
本日写真でピックアップしたのは、そのなかでも2011年に撮影していた2件。
ひとつは兵庫県姫路市南西部の「英賀神社」の拝殿と、
もうひとつは北海道旭川駅(設計/内藤廣)であります。
なぜか、この2題への「強い印象」というものに気付いた次第。
旭川駅は、移動交通手段の発達した現代をリアルに表現している。
撮影の時にはそう強く感じていなかったのですが、
建築としての駅というものを考えたときには
まさに風洞型建築ということが明瞭に伝わってきた。
移動交通手段である列車の移動を確保するためには大開口が不可欠。
一方で豪雪地域である旭川では積雪をどう考えるか、がキモでしょう。
そうすると、全体を囲う屋根とその架構の力学的検討がまずあって、
その内部でのひとの受け止め方を考えていくことになる。
いかにも力学構造から導き出された鉄骨フレームがコンクリート構造と
緊結されて、大屋根を保持させている様子が窺われる。
そういう力学表現が写真のように展開している。
旭川ではこのプラットホームから降りていく空間で木質が「出迎え」ている。
そっちはまた別のこととして、この架構ぶりについて、
つい最近まで建っていた英賀神社拝殿との共通性に気付いた。
旭川駅では列車が移動する風洞だけれど、
この英賀神社拝殿は、ひとが移動参集する風洞として機能してきていた。
(この拝殿は現在は建て替えられる予定)
こういった機能としての「拝殿」そのものは、
日本に根付いた機能性建築としてたくさんあると思うのですが、
この英賀では、そうしてできた屋根が大きく掛けられていて
その「見上げ」可能な空間一杯に「掲額」が奉納され続けてきた。
たぶん、氏子たちが歴史年代を通じて年に1度、プレゼントし続けてきた。
絵のテーマはそれこそ時代背景のままのようで、
キッチュな大衆的表現がまことにたのしくさせてくれていた。
<そのうち一挙公開いたします(笑)>
機能性と建築表現としては似たようなふたつの建築、
さて「優れている」のはどっちなのかなぁと、
ややイジワル気味に(笑)、対比させてみたくなった次第。
あ、いや、内藤さんのつくった駅も大好きなんですよ、ホント。
Posted on 8月 16th, 2019 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究 | No Comments »